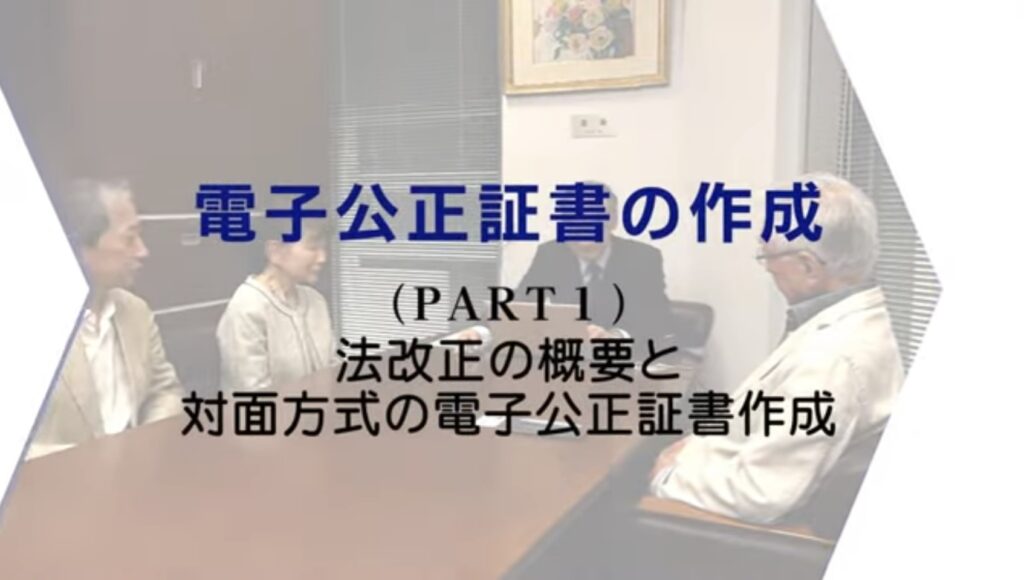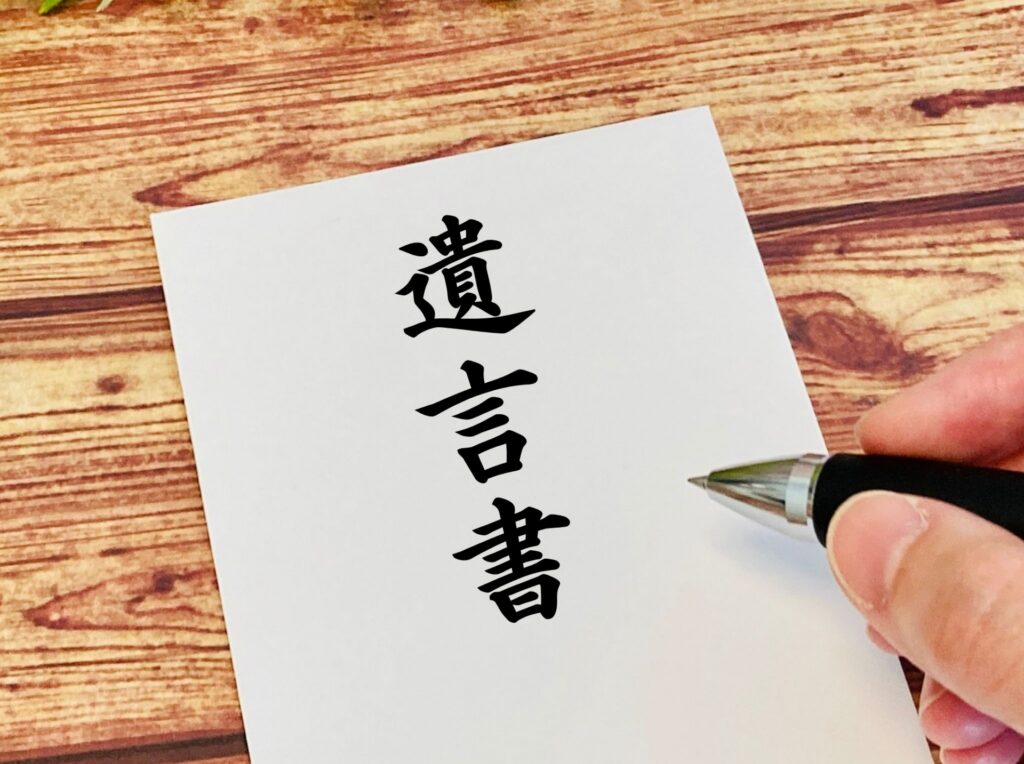
自筆証書遺言
自筆証書遺言については、平成30年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、これまでの制度が一部改正され、以前より使いやすくなりました。
従来の自筆証書遺言は、遺言者が 全文・日付・氏名を自書し、押印する 必要がありました。さらに、書き加え・削除・訂正をする場合には、遺言者がその場所を明示し、変更の旨を付記して署名し、かつ変更箇所に押印しなければならないとされていました。
改正後も基本的な形式は変わりませんが、特に 財産の種類や数が多い場合 に大きな改善がありました。これまで最も面倒だといわれていた 財産目録 については、自書で作成する必要がなくなったのです。
具体的には、財産目録部分については
- ワープロで作成する
- 他人に作成してもらう
- 不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付する
といった方法も認められるようになりました。
ただし、財産目録が自筆でない場合でも、遺言者本人の署名押印 は必要ですので注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記して作成する方式です。作成された遺言は、日本公証人連合会に登録され、原本は公証役場で保管されます。さらに、そのPDFファイルも日本公証人連合会に送信されて保管されるため、仮に公証役場で原本が失われても、そこから再製本が可能となっています。
普通方式遺言の3つの中で、公正証書遺言は最も信用性が高いといわれています。
また、現在「家庭裁判所での検認が不要」なのは、
- 法務局に保管された自筆証書遺言
- 公正証書遺言
の2種類だけです。
検認の手続きでは、法定相続人を確定するために戸籍一式や相続人の連絡先が必要となります。検認は、遺言の有効・無効を判断するものではなく、改ざん防止や現状保存のための手続きです。紛失や隠匿のリスクがないという点で、法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言は大きな安心感があります。
家庭裁判所における検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経なければ効力を発揮できません。これらは自宅で保管されるため、改ざん・紛失・破棄のリスク があるからです。
検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断するためのものではなく、提出時点での状態を確認・保存するための制度です。この手続きを行うことで、改ざんを防止でき、また紛失や破棄があった場合でも家庭裁判所に記録が残るという副次的効果があります。
なお、法務局に保管されている自筆証書遺言 については、検認が不要です。したがって、
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
の2種類のみが、家庭裁判所の検認を経ずに効力を発揮することになります。
自筆証書遺言保管制度について
これまで自筆証書遺言は、自宅での保管が一般的でしたが、紛失・発見されない・改ざん・破棄といったリスクがありました。
この問題を解消するため、平成30年7月に公布された 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 と同時に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」 が制定され、令和2年7月10日から施行 されています。
この制度により、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになり、相続開始後も家庭裁判所の「検認」が不要となりました。
自筆証書遺言保管手続きの流れ
1. 保管申請の準備
- 遺言者本人が法務局に対し保管申請を行います。
- 使用する様式は 法務省のホームページからダウンロード可能 です。各遺言書保管所の窓口にも備え付けられています。
- 申請書等を記載する際は、注意事項をよく読み、記載ミスのないようにしてください。
2. 遺言書の作成(用紙の指定あり)
- 用紙は A4サイズの白紙 を使用。縦書き・横書きの指定はありません。
- 余白は
- 上:5ミリメートル以上
下:20ミリメートル以上
右:5ミリメートル以上
左:20ミリメートル以上
空けます
- 上:5ミリメートル以上
- 記載は片面のみ。各ページにページ番号を振り、閉じずに提出します。
- 字が判読可能であることが必要です。
3. 保管を申請できる法務局
- 遺言者の 住所地、本籍地、または 所有する不動産の所在地 の法務局。
- ただし、すでに他の法務局に遺言書を預けている場合、その法務局が保管場所となります。
4. 予約方法
保管申請には予約が必要です。方法は以下の3つです。
- 法務局手続案内予約サービス(専用サイト)
- 電話予約(手続きを行う予定の法務局へ直接)
- 窓口で予約
5. 申請手続き(遺言者本人が出頭)
予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所へ出頭し、以下を提出します。
- 自筆証書遺言
- 必要事項を記載した申請書
- 添付書類(遺言者本人の本籍記載のある住民票の写し〈3か月以内のもの〉)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1点)
- 手数料:3,900円
※ 法務局窓口で同席できるのは原則として遺言者本人のみです。通訳や手話通訳など、やむを得ない場合は同席が認められることもあります。
6. 保管証の交付
手続き終了後、以下が記載された 保管証 が交付されます。
- 遺言者の氏名・生年月日
- 遺言書保管所の名称
- 保管番号
この保管証は、
- 遺言書の閲覧
- 保管申請の撤回・変更
- 相続人等による証明書請求
の際に必要となるため、大切に保管してください。
また、遺言書を預けた事実を家族に知らせる際も、この保管証を示しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
遺言者本人による遺言書の閲覧
遺言者は、自ら保管を申請した遺言書を閲覧することができます。閲覧方法は次の2つです。
- モニター閲覧:遺言書の画像をモニターで確認
- 原本閲覧:保管されている遺言書の現物を確認
ただし、閲覧できる場所が異なります。
- モニター閲覧:全国どこの遺言書保管所でも請求可能
- 原本閲覧:遺言書が実際に保管されている保管所のみで可能
1.予約と手数料
閲覧の際には予約が必要です。遺言者本人が、閲覧請求書に必要事項を記入し、予約した日時に保管所へ出頭します。
手数料は以下のとおりです。
- モニター閲覧:1回につき 1,400円(収入印紙)
- 原本閲覧:1回につき 1,700円(収入印紙)
添付書類は不要ですが、本人確認のため 顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等) を提示する必要があります。
保管申請の撤回
遺言者本人は、保管している遺言書の申請を撤回することができます。
撤回をしても、遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、法務局での保管という効力はなくなる ため注意が必要です。
1.撤回の流れ
- 撤回書の様式に必要事項を記載
- 事前に撤回の予約を行う
- 遺言者本人が保管所に出頭し、撤回書を提出
- 本人確認書類を提示
※ 氏名や住所に変更があった場合には、その変更を証明する書類(住民票等)の提出が必要です。
※ 撤回には 手数料不要 です。
※ 手続き完了後、保管されていた遺言書が返還されます。
遺言書の変更届
遺言者は、保管申請後に 氏名・住所・遺言執行者の氏名や住所 に変更があった場合、その旨を届け出る必要があります。
1.ポイント
- 届出できるのは遺言者本人、または法定代理人(親権者・成年後見人など)
- 内容そのものの変更は不可(内容を変える場合は新たに遺言書を作成し、再申請が必要)
- 手数料は不要
- 届出は全国どこの遺言書保管所でも可能(郵送も可)
2.添付書類例
- 遺言者本人が届け出る場合:住民票や変更事項を証明する公的書類
- 親権者が届け出る場合:戸籍謄本
- 成年後見人の場合:登記事項証明書
- 未成年後見人の場合:戸籍謄本や抄本
遺言者以外による閲覧等
遺言者が亡くなった場合、相続人等が閲覧や証明書の交付を請求できます。
1.遺言書保管事実証明書の交付
- 全国どこの保管所でも請求可能
- 必要書類
- 遺言者が死亡したことを証明する戸籍謄本
- 請求人の住民票
- 請求人の立場を証明する書類(例:相続人なら戸籍、法人なら代表者事項証明書、成年後見人なら登記事項証明書など)
自筆証書遺言を法務局に保管すれば、公正証書遺言は不要?
法務局に保管された自筆証書遺言の限界
自筆証書遺言を法務局に預けると、遺言書保管官が以下を確認します。
- 遺言者本人であることの確認(本人確認資料による)
- 民法で定められた形式的な記載事項の確認(外形的調査)
しかし、遺言の内容そのものについて相談に応じることはなく、遺言の有効性を保証するものでもありません。
また、遺言者の意思能力(判断能力)についても、会話の中で明らかに問題がある場合を除き、厳密に確認されることはありません。
さらに、提出資料は遺言者本人に関するもののみであり、受遺者や相続人に関する資料は不要です。したがって、遺言者と相続人との関係性を確認することもできません。
このように、法務局での保管は「形式的チェック」にすぎず、金融機関や不動産登記実務で直ちにスムーズに利用できるわけではない という限界があります。
金融機関での実務
金融機関の実務では、法務局保管の自筆証書遺言があっても、相続手続に大きな変化はありません。
多くの金融機関では、遺言書の有無にかかわらず、法定相続人全員の実印と印鑑証明書が揃わなければ、預貯金の解約や払い出しに応じない のが実情です。
例外的に「法定相続情報一覧図」を取得すればスムーズに進む場合もありますが、その証明書を取得するには結局、戸籍など従来と同じ書類が必要になります。
公正証書遺言の強み
一方、公正証書遺言は以下の点で優位性があります。
- 専門性の担保
公証人が相談に応じ、内容を法的にチェックするため、適正な遺言内容となる。 - 意思能力の確認
公証人が遺言者の判断能力を直接確認し、必要に応じて医師の診断書を求める。さらに証人2名が立ち会うため、後日裁判で無効となるリスクが低い。 - 柔軟な作成方法
遺言者が病気等で公証役場に行けない場合でも、公証人が出張して作成可能。署名できない場合でも代筆制度がある。 - 実務上の利便性
- 金融機関での預貯金解約が容易
- 不動産登記の手続きが簡単(相続人の住民票と認印で対応可能な場合がある)
公正証書遺言のデメリット
- 公証人に支払う 作成手数料がかかる(財産の額に応じて高額になる場合もある)
- 作成のために証人2名の立ち会いが必要
財産額別:公正証書遺言手数料
| 財産額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 3億円超~10億円以下 | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円加算 |
※財産が1億円未満の場合は遺言手当として11,000円を別途加算します(祭祀主宰者指定等の手当も別途)。
公正証書遺言の証人・立会人の日当
試算:9,999万円のでの遺言書作成
法律行為:11,000円(遺言)
財産9,999万円:43,000円
日当:10,000円
証書代:250円×通数
お礼:11,000×2名(証人様分)
合計:86,000円+証書代
参考 公正証書遺言作成の流れ
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC