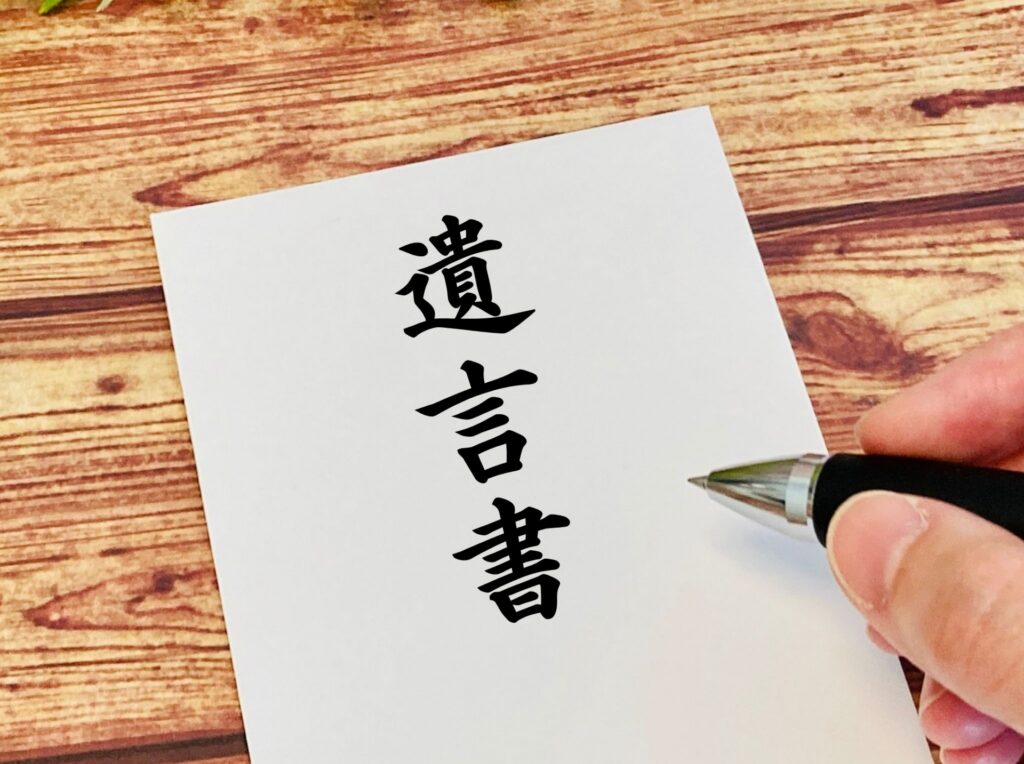
親が子どもを守れるのは、自分が元気で生きている間だけです。
もしも親が亡くなったとき、子どもがまだ未成年であれば、その子の生活や財産を誰が守るのか――。
この問題に備える制度が「未成年後見」です。今回は、遺言による未成年後見人の指定についてわかりやすく解説します。
1. 単独親権者が死亡した場合はどうなる?
離婚や死別などで父母のどちらか一方が親権者となっているケースは珍しくありません。
この「単独親権者」が死亡すると、子どもに親権を行使する者がいなくなります。
その場合、家庭裁判所の手続により未成年後見が開始され、子どもの監護・教育・財産管理を担う「未成年後見人」が選ばれます。
2. 遺言で未成年後見人を指定できる
最後に親権を持っていた親は、遺言によって未成年後見人を指定することが可能です。
あらかじめ「子どもの養育を任せたい人」を遺言で指名しておけば、自分に万が一のことがあった際にも安心です。
ただし、親権を喪失している場合は遺言による指定はできません。
3. 遺言がない場合は家庭裁判所が選任
未成年後見人の指定が遺言にない場合は、子や親族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任します。
しかし裁判所が選ぶ人が、必ずしも希望する人とは限りません。だからこそ、遺言による指定が重要になります。
4. 遺言による指定のポイント
- 形式は遺言に限る(口約束や私的な書面では無効)
- 確実に効力を残すには 公正証書遺言 がおすすめ
- その他に相続や遺贈を含める場合は財産額に応じて別途費用が発生
5. 柔軟な指定方法も可能
- 複数の未成年後見人を指定できる(例:祖父母を2人とも指定)
- 予備的指定ができる(例:第1候補が先に死亡した場合、第2候補を後見人にする)
- 未成年後見監督人を指定できる(例:兄を後見人に、父を監督人に)
- 法人を後見人にすることも可能(弁護士法人・司法書士法人・NPO法人など)
6. 専門家に依頼するメリット
「信頼できる人がいない」「親族に任せるのが不安」という場合は、弁護士や司法書士などの専門職を未成年後見人にする方法もあります。
また、行政書士が関与することで、遺言の作成から将来の備えまでトータルでサポートできます。
7.未成年後見人の主な業務内容
1. 身上監護(身の回りの世話や教育)
未成年者の適切な住居の確保や生活環境の整備
教育機関の選定や入学手続きの管理
健康管理や医療サービスの手配
未成年者が健全に成長できるよう日常の生活全般の支援・指導
社会人として自立できるまでの援助と監督
2. 財産管理と法律行為の代理
未成年者の財産(預貯金、不動産、有価証券など)の管理
財産目録の作成、年間生活費や教育費の予算計画の策定
銀行口座の管理や各種契約の代理締結、遺産分割協議への代理参加
自分の財産と分けて明確な管理を行い、未成年者に不利益を与えない運用
家庭裁判所への定期的な報告(後見事務報告書の提出、収支報告など)
3. その他
未成年者の財産や身上に関する重要な決定の代理
後見終了時の財産引継ぎや関係者への報告
まとめ
未成年の子どもがいる親にとって、「もしも」のときに子どもを誰に託すかは非常に大切な問題です。
遺言によって未成年後見人を指定しておけば、子どもの生活や財産管理を信頼できる人に任せることができます。
亀田行政書士事務所では、
- 公正証書遺言の作成サポート
- 未成年後見人指定に関するご相談
- 遺言と相続全般のサポート
を行っております。お気軽にご相談ください。
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC
