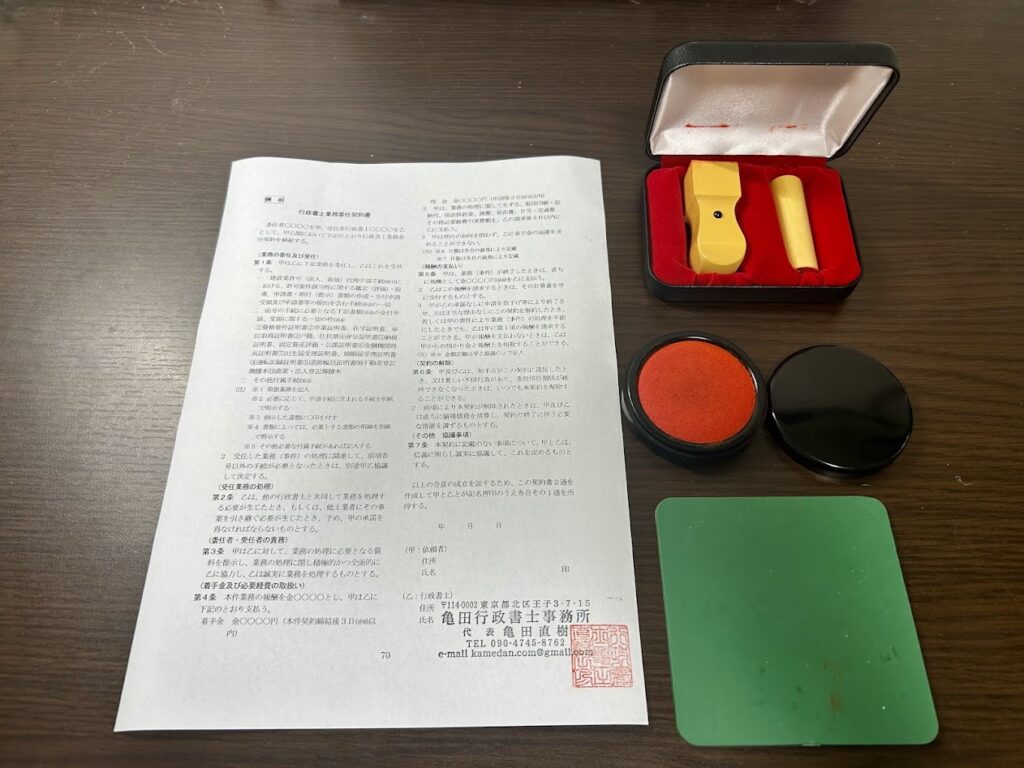✅ はじめに
建設業の経営経験を持つ取締役がいないため、常勤役員等(経管)の設定ができず、建設業許可取得に課題を抱える企業は少なくありません。また、他の企業から経営経験者を招聘して役員にすることにリスクを感じる経営者も多く存在します。
こうした状況を背景に、「補佐者」を設置する企業が非常に増加しています。本編では、補佐者に関する重要なポイントをQ&A形式で詳しく解説します。
💬 Q&A|補佐者に関する詳細解説
Q1. 建設業許可事務ガイドライン(第5条及び第6条関係)2の(6)②を読むと、直接補佐者の経験については、営業所技術者等(専技)の実務経験とは異なり、期間の重複が認められるように思えますが、この理解でよろしいでしょうか?例えば、平成29年10月から財務管理、労務管理を並行して3年間行っていた場合、補佐者になれますか?
A.
財務管理、労務管理、営業運営の各経験については、それぞれ5年以上必要です。
建設業許可事務ガイドライン(第5条及び第6条関係)2の(6)②では、複数の業務を担当する地位での経験について、それぞれの業務経験として当該期間を計算して差し支えないものとされています。
したがって、補佐者の経験と他の実務経験の期間重複は認められます。しかし、本例の場合、財務管理及び労務管理の経験がそれぞれ3年ずつであるため、要件を満たしておらず、直接補佐者となることはできません。なお、これらの期間は並行していても構いませんが、それぞれ5年以上の経験が必要です。
Q2. 建設業許可事務ガイドライン(第5条及び第6条関係)3の(3)①により、補佐者には常勤を求めると理解していますが、その確認資料としては何を提出すればよいですか?
A.
補佐者の常勤性の確認資料としては、以下が例示されています。
- 健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知書の写し
またはこれらに準ずる資料が必要です。
Q3. 建設業法施行規則および建設業許可事務ガイドラインには、補佐者の欠格要件について規定が見当たりません。
営業所技術者等(専技)と同様に、欠格要件に該当する者でも補佐者になれるという理解でよいですか?
また、登記されていないことの証明書、身分証明書、役員等氏名一覧表の提出は不要と考えてよいですか?
A.
従前より、許可の欠格要件は建設業法第8条に規定されており、役員以外の補佐者に関する規定はありません。
したがって、登記されていないことの証明書および身分証明書は不要です。また、東京都の取り扱いとして、役員等氏名一覧表および役員等指名一覧表への記載も不要とされています。
Q4. 財務管理経験を5年有する者が、その役職のまま補佐者になると、後任の育成に支障が出るように思えます。この点についてどうお考えですか?補佐者に就任する際、財務管理・労務管理・業務運営の役職から外れる必要はありますか?
A.
本規定は、持続可能な事業環境を確保するために、過去5年以上の建設業経験を有する役員を置くことを要件とせず、事業者全体として適切な経営管理体制を有することを要件としたものです。
許可審査では、事業者全体として建設業法施行規則第7条に定める基準を満たしているかが確認されますが、東京都として、会社の人事配置や経営方針に干渉することはありません。
なお、建設業許可事務ガイドライン(第7条関係)1の(1)⑧にて、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験および直接補佐について解説されていますが、職層について限定はありません。
Q5. 現在の常勤役員等(経管)を変更して補佐者を置く場合、提出書類(確認資料を除く)は何が必要ですか?
A.
以下の書類が必要です。
① 様式第22号の2 変更届出書(第1面)
② 別紙 役員等の一覧表(※常勤役員等(経管)の記載が必要です。)
③ 別閉じ用表紙
④ 様式第75-2 常勤役員等(経管)および常勤役員等(経管)を直接に補佐する者の証明書(第1面~第4面)(※同一人物が兼務する場合でも、3種の直接補佐者それぞれの作成が必要です。)
⑤ 別紙1 常勤役員等(経管)の略歴書
⑥ 常勤役員等(経管)を直接に補佐する者の略歴書
⑦ 後任者それぞれについて、手引きに示された各確認資料
⑧ 前任者の在職確認資料(※健康保険証の写しが必要です。)
Q6. 直接補佐者は、常勤役員等(経管)と同列でも問題ありませんか?
A.
同列は認められません。直接補佐者は、常勤役員等(経管)の直属の部下である必要があります。
Q7. 直接補佐者の確認資料として、手引きでは原則として当時の資料(自社経験のみ)が数年分必要とされていますが、例外としてはどのようなものが想定されますか?例えば、後から事実証明する形で資料を提出することは可能ですか?
A.
当時の資料がどうしても用意できない場合に限り、直近の5年以上の資料でも対応可能です。
事実証明の基礎となる資料が必ず必要となりますので、それを提出していただき、個別に判断します。
Q8. 直接補佐者を置く場合、事前に相談する必要はありますか?
A.
各社の状況に応じて提出可能な証明資料が異なるため、当面の間は審査窓口に事前相談を行ってください。
Q9. 直接補佐者の経験は、直属のものとしての経験が必要ですか?
A.
申請時点で、常勤役員等(経管)の直属の部下である必要がありますが、過去の経験については必ずしも直属である必要はありません。
Q10. 直接補佐者や施工規則第7条第1号ロ(1)該当の財務管理、労務管理、業務運営の経験は、具体的にどのような部署が該当しますか?
A.
部署名は法人ごとに異なりますので、業務規程、稟議書等により具体的に行われている業務内容を基に審査します。
特に業務運営については、建設業における中長期的な年間計画の策定、資材調達、工事実施に関する業務を行っている部署であることを確認します。
Q11. 常勤役員等(経管)の上位に位置する者は、直接補佐者として認められますか?
A.
建設業許可事務ガイドライン(第7条関係)1の(1)⑧では、「直接に補佐する」とは、組織体系上および実態上、常勤役員等(経管)との間に他の者を介在させず、当該常勤役員等(経管)から直接指揮命令を受け、業務を常勤で行うことをいいます。
このため、直属の部下であることが必要です。
Q12. 経営業務管理責任者を直接補佐者として置くことはできますか?
A.
新設会社において5年以上の経営経験を証明した経営業務管理責任者(元経営業務管理責任者を含む)、または申請会社において5年以上経営業務管理責任者を務めた者は、当該申請会社において財務管理、労務管理、業務運営の各経験をそれぞれ5年以上有するものとみなされます。
この者を申請会社の直接補佐者として置くことは可能です。ただし、申請時点で常勤役員等(経管)の直属の部下である必要があります。
✅ まとめ
補佐者制度は、常勤役員等(経管)を補う形で経営体制を整備するための重要な制度です。
要件を正確に理解し、証明資料を確実に準備することが、スムーズな許可取得の鍵となります。
🔜 次回予告
次回は「【第13回】営業所技術者等(専技)」編として、技術者要件や配置に関する詳細を解説します。
✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 最短申請可能! お急ぎの方もスピーディーに対応します。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC