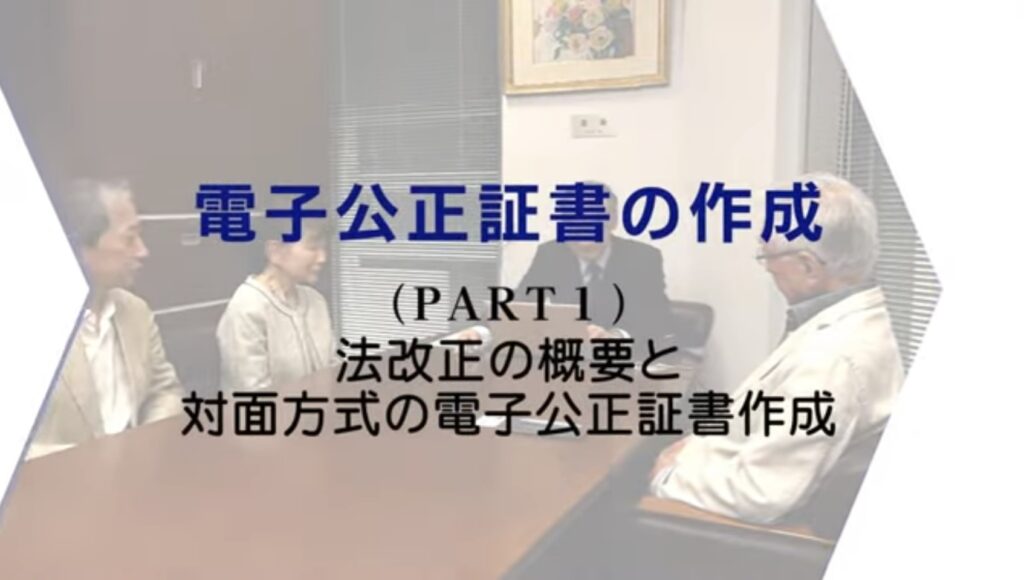1.受託者となる者の資格(信託法第7条)
受託者は、他人の財産を管理・運用する立場にあるため、法律行為の制限がある未成年者は受託者となることができません。一方で、それ以外の者、すなわち個人・法人を問わず、成年であれば受託者となることが可能です。
2.受託者の権限と義務
(1)権限(信託法第26条)
受託者は、委託者から信託された信託財産について、管理・処分、その他信託目的達成のために必要な一切の行為を行う権限を有します。
ただし、一定の行為については信託契約により制限することが可能です。例として、「自宅の売却を禁止する」「売却には長女の同意が必要とする」などの規定を設けることができます。
(2)信託債務と責任の原則
受託者は、信託財産について名義人となり、重要な管理権限を持つ一方で、重い法的責任を負います。信託契約に基づく取引で生じた債務は、原則として信託財産から弁済されるものの、それで足りない場合は受託者個人の財産からも回収され得るという点に注意が必要です。つまり、受託者は信託の債務について無限責任を負うことになります。
この点は非常に重要であり、受託者は委託者・受益者の“連帯保証人”的立場にあるという認識が不可欠です。
たとえば、信託財産の修繕資金として融資を受けた際、その返済が信託財産だけでは足りなければ、債権者は受託者個人に対しても返済を請求できることになります。これは受託者候補者に対して、契約前に明確かつ強く説明すべきポイントです。
3.受託者の法的義務(信託法より)
(1)権限逸脱行為の取消し(第27条)
受益者は、受託者が信託の権限を超えて行った行為について、一定の条件下でその行為を取り消すことができます。
(2)善管注意義務(第29条)
受託者は、善良な管理者の注意義務(いわゆる“善管注意義務”)をもって信託事務を遂行しなければなりません。
ただし、信託契約で別段の定めを置くことで、この注意義務を軽減することも可能です(第29条第2項但書)。
(3)忠実義務(第30条)
受託者は、信託の目的に従い、自己の利益を優先せず、受益者の利益のために忠実に職務を行う義務があります。利益相反行為や競合行為は、原則として禁止されます。
(4)利益相反行為の制限(第31条)
受託者は信託財産の名義人であるため、自身の判断で信託財産を処分できる立場にあります。しかし、受託者と受益者の利益が対立する取引(利益相反行為)は原則として無効です。
ただし、事前に信託契約等で許可を得ている場合や、受益者の承認を得ている場合には例外的に許容されます(第31条第2項)。
(5)公平義務(第33条)
受益者が2人以上いる場合、受託者はその全ての受益者に対し公平に職務を遂行しなければなりません。
実務上、受益者を複数人設定することは可能ですが、本当に公平な処理が可能か、分配に不公平感が生じないか等を慎重に検討した上で設定する必要があります。(公平性維持が難しいため当事務所ではおすすめしていません)
(6)分別管理義務(第34条)
受託者は、自身の固有財産および他の信託からの財産とは明確に分けて、信託財産を個別に管理する義務があります。これにより、財産の混同や誤使用を防止します。
(7)信託事務の処理に関する第三者の選任・監督(第35条)
受託者は、必要に応じて第三者に信託事務の一部を委託することが可能です。ただし、選任・監督については受託者が責任を負います。
(8)報告義務(第36条)
委託者または受益者から請求があった場合、受託者は信託事務の処理状況および信託財産の状況について報告する義務があります。
(9)損害賠償責任(第40条・第41条)
受託者が任務を怠り、信託財産に損害が生じた場合、受益者は当該損害の賠償や原状回復を請求することができます。
受託者が法人である場合、その役員に悪意または重過失が認められるときは、法人と連帯して責任を負うことになります。
(10)差止請求(第44条)
受益者は、受託者の信託義務違反行為が差し迫っている場合、当該行為の差止めを請求することが可能です。
4.受託者が複数いる場合の対応(信託法第80条)
受託者が2人以上いる場合、信託契約に特別な定めがない限り、信託事務は受託者の過半数によって決定されます。また、契約により個別の役割分担を定めることも可能です。
ただし、実務上は受託者を原則として1名とするのが望ましいとされています。
なぜなら、複数受託者による運用は意思決定の遅延や対立のリスクがあるためです。家族信託のメリットである「迅速かつ柔軟な意思決定」を活かすためにも、受託者は可能な限り1名に絞り、必要な場合にのみ後継受託者や予備受託者を設定する設計が望まれます。
5.受託者の帳簿作成・保存義務について(信託法第37条関連)
信託における受託者は、信託財産の管理・処分に伴い、一定の帳簿や書類を作成・保存し、必要に応じて受益者等へ報告・開示する義務を負います。以下、信託法第37条等に基づき、受託者の帳簿等の作成義務・保存義務について整理します。
● 作成義務
受託者は、信託財産に係る帳簿を随時作成する必要があります。
● 保存期間
帳簿は作成後10年間の保存が義務付けられています。
※ただし、受益者に帳簿の写し等を交付した場合、保存義務は免除されます。
● 報告義務・閲覧請求
- 受託者に報告義務はありません。
- 受益者からの閲覧・謄写の請求には、一定の例外を除き応じる必要があります。
● 実務上の取り扱い
信託帳簿といっても、必ずしも会計実務上の厳格な帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)を作成する必要はありません。特に、生活費の管理等を目的とした簡易な信託の場合は、次のような簡便な方法が実務上認められています。
- 出納帳、家計簿の作成
- 預金通帳の該当箇所に使用目的を記載する等の方法
6. 信託事務の処理に関する書類(信託法第37条第5項)
● 作成義務
信託事務の処理に関連して、受託者が作成・受領した書類についても、随時作成または取得することが求められます。
● 保存期間
これらの書類も、作成・取得後10年間の保存が必要です。
※受益者に写し等を交付した場合、保存義務は免除されます。
● 報告義務・閲覧請求
- 報告義務はありません。
- 受益者は閲覧・謄写請求が可能です。
● 対象書類の範囲
信託事務の処理に関する書類には、以下のようなものが該当します:
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
- 建築請負契約書 など
※注意:受託者個人のメモや、法人受託者の社内稟議書のように私的・内部的な資料は対象に含まれません。
7. 信託財産の状況に関する書類(信託法第37条第2項)
● 作成義務
受託者は、毎年1回、一定の時期に以下の書類を作成する必要があります:
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 財産目録等(信託財産の状況資料)
実務上は、確定申告時期(1月~12月)に合わせて作成するケースが多く見られます。
● 保存期間
信託の計算期間終了日から起算して10年間の保存が必要です。
※受益者に写し等を交付した場合、保存義務は免除されます。
● 報告義務・閲覧請求
- 報告義務があります。
- 信託契約で別段の定めを設ければ、報告義務の軽減・免除も可能です。
- 受益者および利害関係人は、閲覧・謄写請求を行うことができます。
● 実務上の取り扱いと様式
信託の目的に応じて、作成すべき書類の内容や様式は異なります。
資産運用型の信託の場合
- 貸借対照表・損益計算書等の作成が必要
- 会社会計実務の形式に準拠したものである必要はありませんが、財務状況を把握できる内容が求められます。
管理型信託(例:居住用不動産の管理など)の場合
- 財産目録の作成で足りるとされています。
- 信託契約書の別紙として添付される「信託財産目録」などがこれに該当します。
- 収益が生じる場合(例:賃料収入、預金利子など)は、確定申告書の控えを添付することで代替することも可能です。
| 書類の種類 | 作成時期 | 保管期間 | 報告義務 | 閲覧・謄写請求 | 保存免除条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託帳簿(第37条1項) | 随時 | 作成後10年 | なし | 受益者から請求あれば可 | 写し等交付で免除 |
| 信託事務の処理書類(第37条5項) | 随時 | 作成・取得後10年 | なし | 受益者から請求あれば可 | 写し等交付で免除 |
| 信託財産の状況書類(第37条2項) | 年1回(例:確定申告時) | 清算結了から10年 | 原則あり(契約により軽減・免除可) | 受益者・利害関係人は可能 | 写し等交付で免除 |
8.受託者の報酬設定の意義と実務上の考慮
将来的に親の介護などが必要となる場面では、家族の一員として支援を行うだけでなく、受託者としての責任を負う対価として、あらかじめ信託契約書に報酬の定めを設けることが有効です。家族間では金銭の話がしにくい場合もありますが、専門家の立場から制度的・法的に提案することは適切かつ現実的な選択肢です。
また、報酬を信託財産から支払うことで、親からの贈与とは異なり、受益者の判断能力が喪失しても実行可能であり、結果として信託財産の減少を通じた相続税対策としても活用できます。
ただし、受託者が個人である場合、受け取る報酬は「雑所得」として所得税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります。そのため、税務処理についても理解と準備が求められます。
9. 信託報酬の法的位置付け(信託法第54条第1項)
受託者が報酬を受け取るには、信託契約に信託報酬の定めを明記する必要があります。定めがない場合、報酬は発生しません。
契約に定めることで、信託財産の中から報酬を支払うことが可能となり、贈与ではない形で受託者に対価を支払うことができます。
- 信託報酬の支払いは、受益者の判断能力が喪失した場合でも可能
- 受託者が親族であっても、適切な報酬設定は相続税対策として有効
- 一方で、税務上、過度な報酬設定は贈与とみなされる可能性があるため、税理士と協議のうえ慎重に設計する必要があります。
10. 信託報酬の決定方法と水準の参考
信託法上、報酬額の上限は明示されていません。そのため、信託者・受託者間の合意により柔軟に設定可能です。以下のような設定が実務上行われています。
- 家庭裁判所が定める成年後見人の報酬基準を参考にする
- 管理対象である収益不動産の家賃に対する一定割合で設定する
● 成年後見人報酬の参考基準(家庭裁判所目安)
| 財産額 | 月額報酬の目安 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 月額2万円 |
| 1,000万円〜5,000万円以下 | 月額3〜4万円 |
| 5,000万円超 | 月額5〜6万円 |
● 信託契約書上の定めの例
「受託者は、信託財産に属する〇〇不動産の家賃収入の○%を上限として、月額〇〇円を信託報酬として受け取ることができる。」
※報酬の金額や算定方法は、後に税務上の贈与と誤認されないよう、明確かつ合理的な基準で設定することが大切です。
11. 税務上の注意点
- 受託者が受け取る信託報酬は、雑所得として課税対象となります。
- 年間20万円を超える場合、確定申告が必要
- 受益者側では、信託財産が収益不動産である場合、支払った信託報酬を必要経費として計上できる可能性があります。
- ただし、判断は個別事情により異なるため、税理士との事前相談が必須です。
12. 後継受託者の検討
信託期間が数年に及ぶ場合、受託者が死亡・認知症・病気等により職務継続が困難になるリスクがあります。そこで以下のような対策が推奨されます。
- 後継受託者の定め(例:受託者が就任不能となった場合は〇〇が後継受託者に就任する)
- 法人受託者の検討(永続性・専門性の確保)
受託者が欠けた状態が1年間継続すると信託は終了してしまうため、信託契約内で明確に後継受託者を指定しておくことが重要です。
また、信託契約で受託者が欠けた場合に備えた受益者による新受託者の選任権限の設定なども有効です。これが設定されていない場合は、裁判所に利害関係人から申し立てを行い、後継受託者を選任する必要があります。
【まとめ】
家族信託制度は、財産の円滑な管理と承継を可能にする有効な仕組みであり、特に高齢化が進む現代社会において、その重要性は年々高まっています。
しかしながら、受託者には信託財産の名義人として極めて重い責任と法的義務が課されるため、制度への正しい理解と、契約内容の適切な設計が不可欠です。信託契約の中では、受託者の選定、権限と責任、報酬設定、帳簿管理、後継体制の整備など、検討すべき事項が多岐にわたります。
家族間での信頼関係を前提とする制度ではありますが、その信頼を守るためにも、制度を制度として正しく機能させるための法的・実務的なサポートが必要です。
【家族信託のご相談は、亀田行政書士事務所へ】
亀田行政書士事務所では、家族信託の設計・契約書作成をはじめ、受託者の業務サポート、報酬設計、税務上の注意点に関する助言など、総合的な支援を提供しております。
信託は「契約」であり、「制度設計」です。だからこそ、一人ひとりのご家族の状況や想いに丁寧に寄り添った提案と設計が必要です。当事務所では、制度の形だけでなく「家族のかたち」に応じた信託を一緒に考えてまいります。
初回相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC