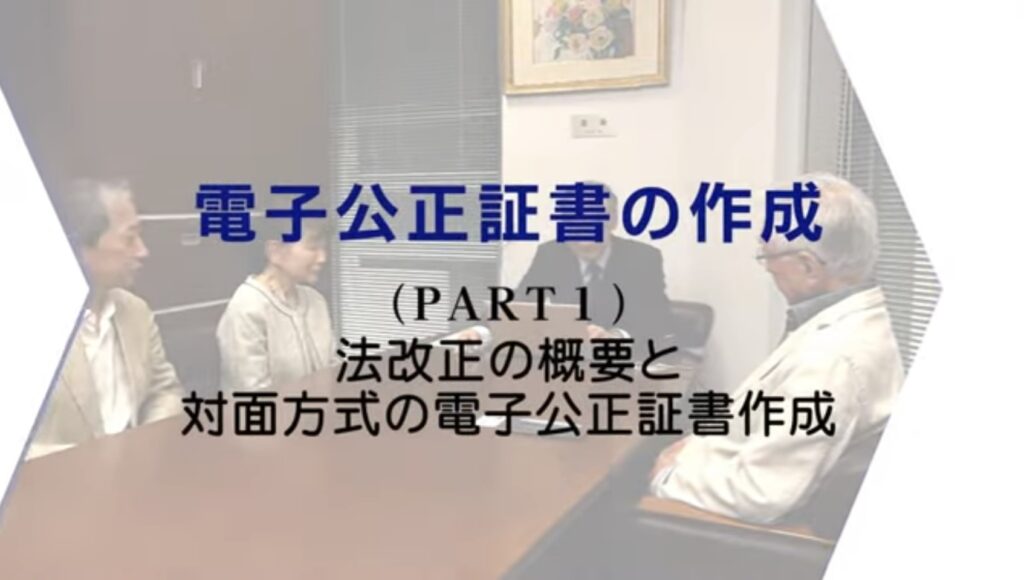任意後見制度の概要
任意後見制度とは、
① 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、
② 将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活・看護・財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、
③ 公証人が作成する公正証書で締結しておき、
④ 本人の判断能力が低下した際に、本人または任意後見人を引き受けた人などが家庭裁判所に対して「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、任意後見受任者は「任意後見人」となります。その任意後見人が本人を代理して契約を締結するなどして、本人の意思に従った適切な保護・支援を行う制度です。
即効型
速攻型とは、任意後見契約を締結した直後に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる方式をいいます。
例えば、軽度の認知症などにより判断能力はあるものの低下が見られる場合、任意後見契約を締結し、その直後に任意後見監督人の選任を申し立て、すぐに任意後見人による保護を受けることができます。
将来型
将来型とは、移行型と異なり、任意後見契約と同時に財産管理等に関する事務委任契約を締結しない方式です。
本人の判断能力がなくなったか、または低下した段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、専任の審判が確定してから任意後見契約の効力が生じます。
日本の国民性から、任意後見監督人の選任申立てがなかなか行われない傾向があり、その点が問題となります。また、中には「任意後見契約さえ結んでおけば、監督人が選任されなくても任意後見人として財産管理などができる」と誤解されている方もいます。
移行型
日本公証人連合会が推奨しているのが「移行型」と呼ばれる方式です。
これは「事務委任契約」と「任意後見契約」の2つを同時に締結します。
この形式では、本人に判断能力がある間は任意後見受任者として本人から依頼された財産管理のみを行います。そして本人の判断能力が低下すると、最終的に家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が発効して、任意後見受任者が任意後見人となり、契約に基づいた財産管理を行うことになります。
法定後見制度との比較
法定後見の場合、まず「補助」については、本人の意思で申し立てられた時、通常は何らかの能力低下があると判断されるため、実務上は本人の意思のみで開始の審判がされる事例が多くあります。
一方、「後見」または「保佐」の場合は、本人がそれぞれの類型に該当する状態になった場合に、初めて開始の審判がされます。
任意後見契約を結ぶ意義
自分の財産管理を任せられる信頼できる人がいる場合、その人との間で任意後見契約を締結しておくと安心です。
特に「移行型」を締結しておけば、判断能力が不十分であることを明確に確信できない限り家庭裁判所に監督人の選任申立てを行いにくいことや、仮に申立てをしても手続に時間がかかることがあります。そうした期間中は、事務委任契約を利用して本人を保護・支援することができます。
このようにして任意後見人となった人は、本人の判断能力が低下したとしても、本人の意思に従った適切な行為を行うために、意思疎通ができる間に本人の理想のライフスタイルを十分に確認し、可能な限りこれに沿った生活ができるよう支援していくことが重要です。
任意後見契約と契約自由の原則
任意後見契約は「契約自由の原則」に則っています。
契約自由の原則は「私的自治の原則」とも呼ばれ、所有権絶対の原則、過失責任の原則と並ぶ近代司法の三大原則の一つです。
その内容は、契約当事者は合意によって契約を自由に決定できるという民法上の原則です。つまり、契約締結の相手方を誰にするか、契約を締結するか否か、契約の内容、締結方式を自由に決めることができます。
ただし、任意後見契約については、民法の強行規定に反する内容を定めることはできませんし、契約締結の方式についても「公正証書」によらなければ効力を生じません。その意味では内容を自由に定められますが、最低限必要な要件がありますので、公証人にご相談ください。
特に、公証人が準備している任意後見契約に関する「代理権目録」には、財産管理に必要な基本的な代理権が網羅されています。しかし、当事者間で誤解を生じさせないよう特に明記してほしい事項がある場合は、積極的に相談してみてください。
任意後見人の選定
契約の相手方も自由に選ぶことができます。任意後見人には委任者が信頼できる人を選べますので、親族、特に法定相続人の中から選ぶことが一般的です。その場合は、その人を任意後見受任者として契約を締結すればよいでしょう。
ただし、任意後見契約に関する法律第4条1項3号および民法847条によれば、次の者は任意後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をしている者、または訴訟をした者とその配偶者・直系血族
- 不正行為、著しい不品行、その他任務に適さない自由がある者
任意後見契約に必要な書類
必要な書類としては、
- 委任者(本人)
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本(全部事項証明書。本籍の記載があるもの)
・住民票(ただし、住民票については他の提出書類で住所等が確認できるため不要とする公証役場もありますので、事前に公証役場へ確認が必要です) - 任意後見受任者
・印鑑登録証明書
・本籍の記載のある住民票
いずれも契約作成時点で発行から3か月以内のものが必要になります。
手数料
任意後見契約にかかる手数料は以下のとおりです。
- 基本手数料:11,000円(原本4枚までを含む)
- 正本・謄本作成費用(いわゆる「紙代」)
・本人用正本1通
・任意後見受任者用正本1通
・東京法務局に登記嘱託するための正本1通
→計3通。1枚あたり250円の手数料が必要になります。
これ以外に、東京法務局の登記手続きに関して次の費用が必要です。
- 登録免許税(印紙代):2,600円
- 登録手数料:1,400円
- 往復の書留郵便料 等
なお、移行型の場合は事務委任契約が加わるため、基本手数料11,000円がさらに加算されます。文章量も長くなるため、「紙代」も増加します。
また、複数の任意後見受任者を定める場合には、基本手数料や登記手数料などは別々に計算されますので、その分費用も高くなります。
任意後見人の登記
かつての「禁治産・準禁治産制度」では、戸籍に記載される方式であったため、利用者が少ない状況でした。これを改めた成年後見制度では、任意後見契約を締結した場合、公証人が東京法務局に嘱託して登記することになりました。
さらに、家庭裁判所が任意後見監督人の選任審判をして確定した場合には、家庭裁判所からも任意後見監督人が選任された旨の登記嘱託がなされます。
この両者が揃うことにより、任意後見人は東京法務局から 「登記事項証明書」 の交付を受けることができます。この証明書には、任意後見人の氏名や代理権の範囲が記載され、これにより任意後見人は自らの代理権を証明できます。取引の相手方もこの登記事項証明書を確認することで、任意後見人を法定代理人として安心して取引できるのです。つまり、登記事項証明書は法務局が発行する信頼性の高い委任状として機能します。
登記される事項と変更・終了手続き
- 任意後見監督人選任前
登記されるのは、本人および任意後見受任者を特定する事項と代理権の範囲です。 - 任意後見監督人選任後
登記されるのは、本人・任意後見人・任意後見監督人を特定する事項と代理権の範囲です。
登記事項に変更があった場合には、変更登記手続きを行わなければなりません。
また、本人の死亡等により任意後見契約が終了した場合には、終了登記手続きをしなければなりません。これらの変更・終了手続きは、当事者が行う必要がありますのでご注意ください。
登記の手続きは東京法務局に嘱託されますが、実務上はお近くの法務局で取り扱える場合もあります。ただし支局など一部の法務局では対応できないこともあるため、事前に電話で確認が必要です。なお、当然ながら手続きの内容によって添付書類は異なりますので、こちらも法務局で確認してください。
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC