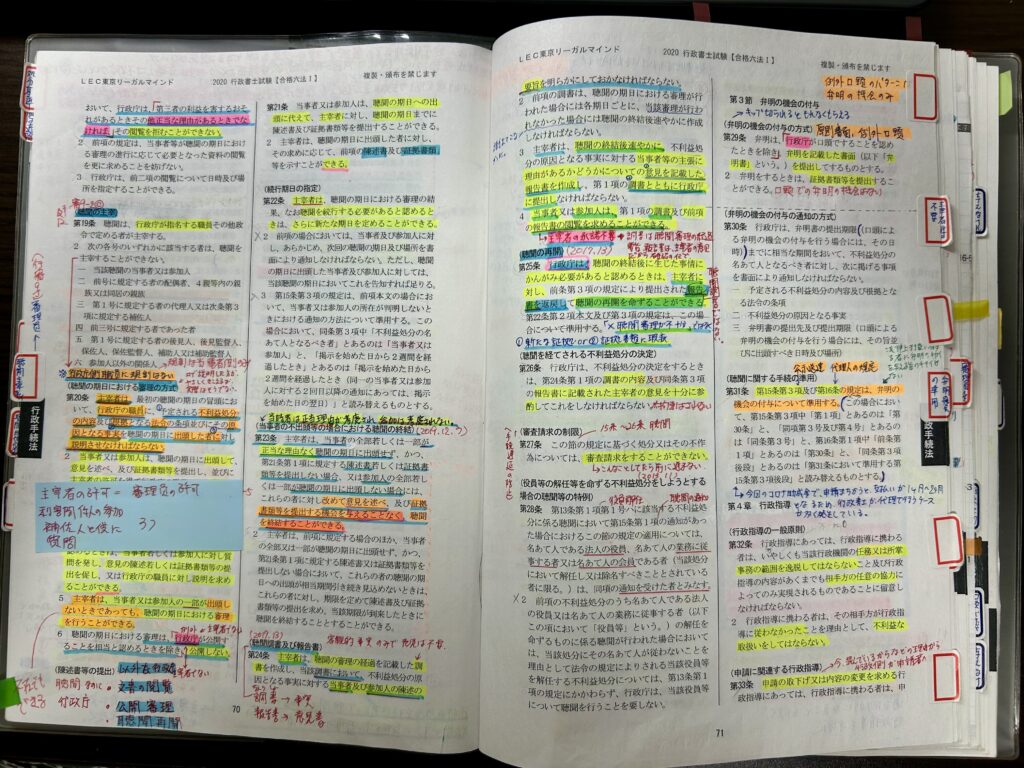
こんにちは。亀田行政書士事務所です。
行政書士試験を受験される皆さま、ラストスパートの学習本当にお疲れさまです。
私自身が合格を目指して勉強していた頃、毎朝「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」の条文を繰り返し読み込んでいました。条文は試験本番でもそのまま出題されやすいため、直前期の学習法としてとても有効です。
今回は行政書士試験で頻出の 行政手続法 第1条(目的)と第2条(定義) を中心に、出題ポイントを徹底解説していきます。
行政手続法 第1条:目的条文を攻略する
条文の要点
行政手続法の第1条は、試験でも繰り返し問われる最重要部分です。
- 対象:処分・行政指導・届出・命令等
- 目的:行政運営の公正の確保、透明性の向上
- 国民の権利利益の保護に資する
特に「語句の入れ替え」問題として狙われやすいので、省略せず 全文暗記 がおすすめです。
また、第1条から行政手続法が「一般法」であることも理解しておくと得点に結びつきます。
行政手続法 第2条:定義を徹底解説
第2条は「定義」を問う問題が非常に多く、暗記だけでなく意味を理解することが重要です。
1. 処分
- 行政庁の処分、公権力の行使に当たる行為
- 過去の試験でも繰り返し出題
2. 申請
- 自己に利益を付与する処分を求める行為
- 「自己」であり「特定の者」ではない点がポイント
- 許可・認可だけでなく免許も含まれる
3. 不利益処分
- 義務を課したり権利を制限する処分
- ただし「申請拒否」や「事実上の行為」など例外あり
- 出題頻度が非常に高い
4. 行政機関
- 内閣に置かれる機関や国家行政組織法に基づく機関など
- 職員自体も行政機関に含まれる点がポイント
- 地方公共団体では「議会」が除外される
5. 行政指導
- 行政目的を実現するために行う指導・助言・勧告など
- 処分には当たらない
- 例:災害時の避難勧告
6. 届出
- 行政庁への通知行為(申請に該当するものは除く)
- 行政庁に応答義務がない点が特徴
- 例:提出届、36協定届
7. 命令等
- 審査基準、処分基準、行政指導指針など
- 丸暗記必須の重要ワード
試験で狙われやすいポイント
- 第1条(目的条文)は語句の入れ替え問題が定番
- 第2条の定義では「申請」と「不利益処分」の違いが問われやすい
- 「命令等」は暗記で対応するしかない
- 条文を毎日読むことで自然に記憶が定着
効果的な学習法
- 毎朝の条文読み込み → 記憶の定着に最適
- 定義は表やフローチャートにまとめると理解が深まる
- 過去問で出題パターンを確認し、知識を補強する
まとめ
行政手続法の第1条(目的)と第2条(定義)は、行政書士試験における最重要ポイントです。
ここを確実に押さえておくことで、得点アップはもちろん、他の科目の理解にもつながります。
直前期こそ「毎日の条文学習」を習慣にし、合格へのラストスパートを駆け抜けてください。
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC
