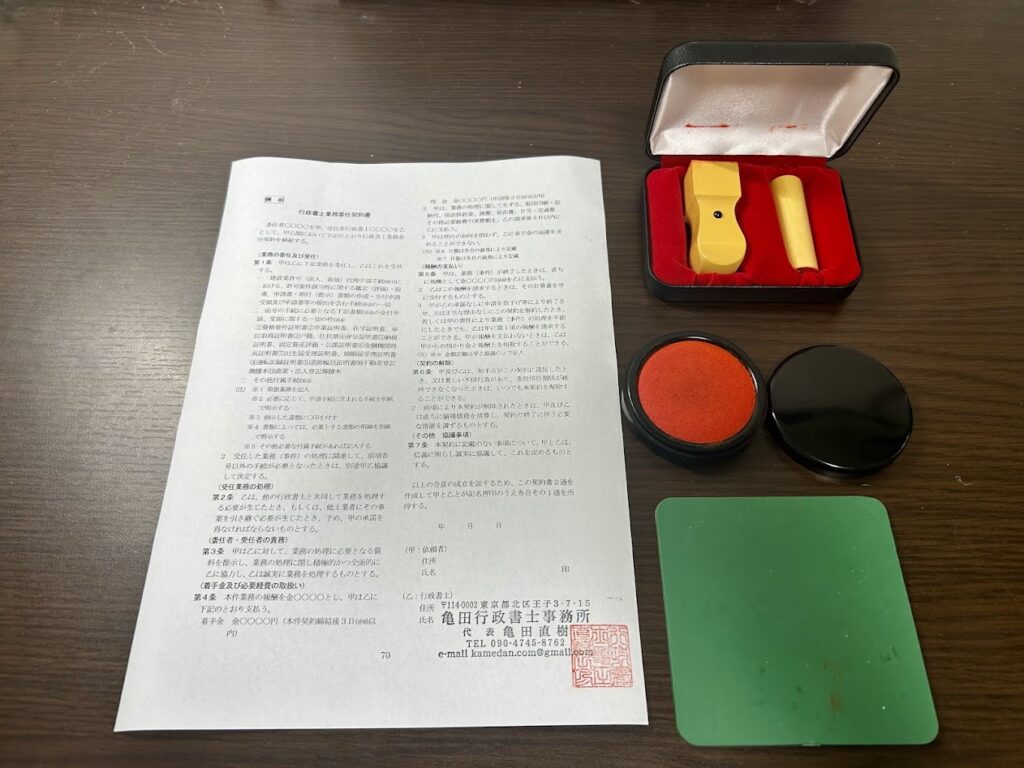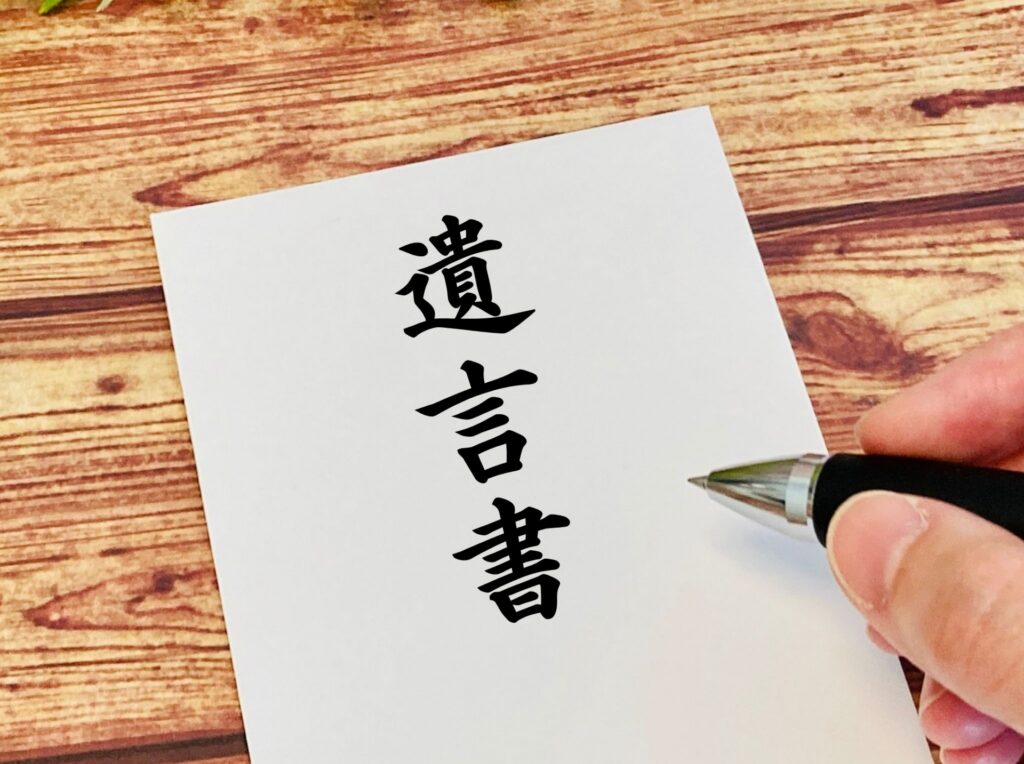
遺言書がないとどうなる?
遺言書がなければ、相続は民法の法定相続分に基づいて分けることになります。
一見シンプルに思えますが、実際には「誰がどの財産を相続するのか」という具体的な分け方をめぐって意見がまとまらず、遺産分割協議に時間と労力を要するケースが多いです。
相続人同士で話し合いが難航すれば、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあり、家族関係が悪化してしまうことも少なくありません。
書遺言を作るメリット
- トラブルを防げる
「遺言者がこう決めたのだから仕方がない」という心理が働き、相続人同士の争いを抑える効果があります。 - 手続きがスムーズ
公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きが不要です。
不動産の名義変更や金融機関での相続手続きもスムーズに進められます。 - 形式の不備がない
公証人が作成するため、法律的に無効となる心配がありません。 - 遺言執行者を指定できる
遺言執行者を指定すれば、司法書士に依頼しなくても相続人自ら登記申請が可能となり、費用を抑えることができます。
「相続させる」と「遺贈する」の違い
- 相続させる:法定相続人に財産を渡す場合の表現
- 遺贈する:法定相続人以外に財産を渡す場合の表現
農地については特に注意が必要で、相続であれば農業委員会の許可は不要ですが、遺贈の場合は許可が必要になる場合があります。
また、兄弟姉妹に相続させたい場合、その兄弟がすでに高齢であることから「甥・姪に残したい」と考えるケースもあります。
ただし兄弟が生存していれば、甥・姪には直接相続させられません。その場合は「予備的遺言」を用いて、兄弟が先に亡くなっていた場合に甥・姪に相続させる、と書くことが可能です。
遺言の文例
文例1:配偶者にすべて相続させる場合
第1条 遺言者は、遺言者の有するすべての財産(不動産、預貯金、債権、現金、家財道具その他一切の財産)を、遺言者の妻 〇〇(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として〇〇を指定する。
文例2:配偶者と子どもに分ける場合
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産およびこれに付属する家財道具その他の財産を、遺言者の妻 〇〇(生年月日)に相続させる。
(不動産の表示:登記簿の表題部を記載する)
第2条 遺言者は、前条記載不動産を除くその他の不動産を、遺言者の長男 〇〇(生年月日)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者のその他一切の財産(預貯金、債権、現金、その他の動産)を、妻〇〇に10分の4、長男〇〇に10分の1、長女〇〇に10分の5の割合で相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として〇〇を指定する。
まとめ
遺言書がないと法定相続に従って分けるしかなく、相続人同士での調整に苦労することが多いです。
一方、公正証書遺言を残しておけば、トラブル防止・手続きの円滑化・費用の節約につながります。
相続をめぐるトラブルを避けたい方は、ぜひ早めに遺言の作成をご検討ください。
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC