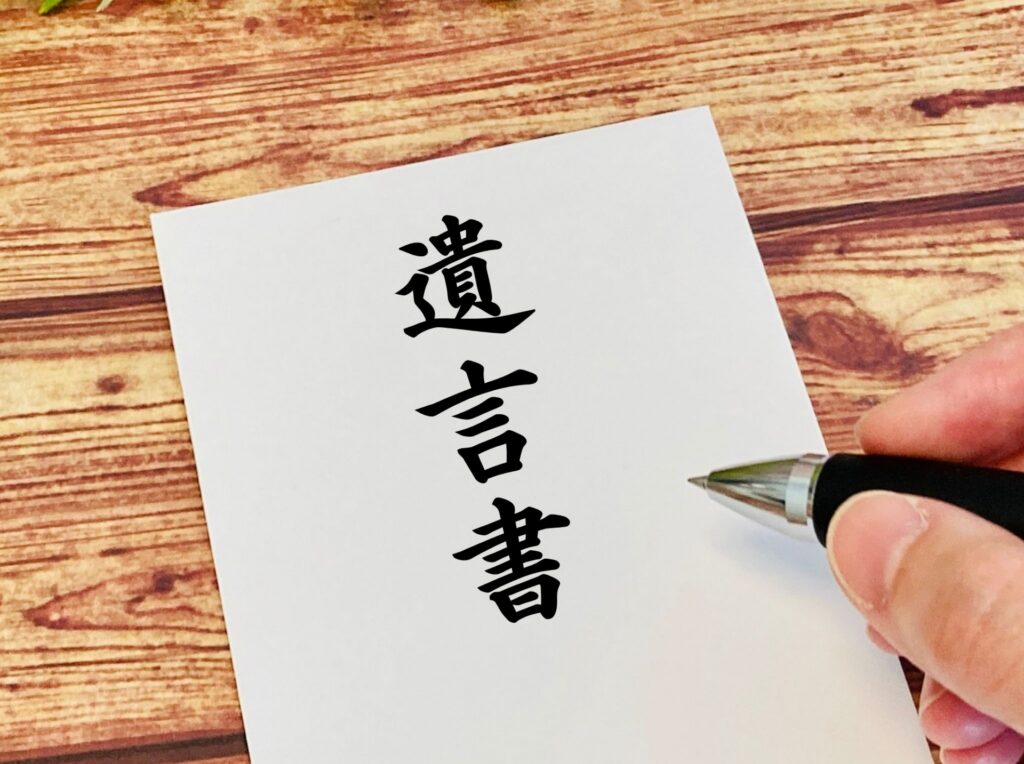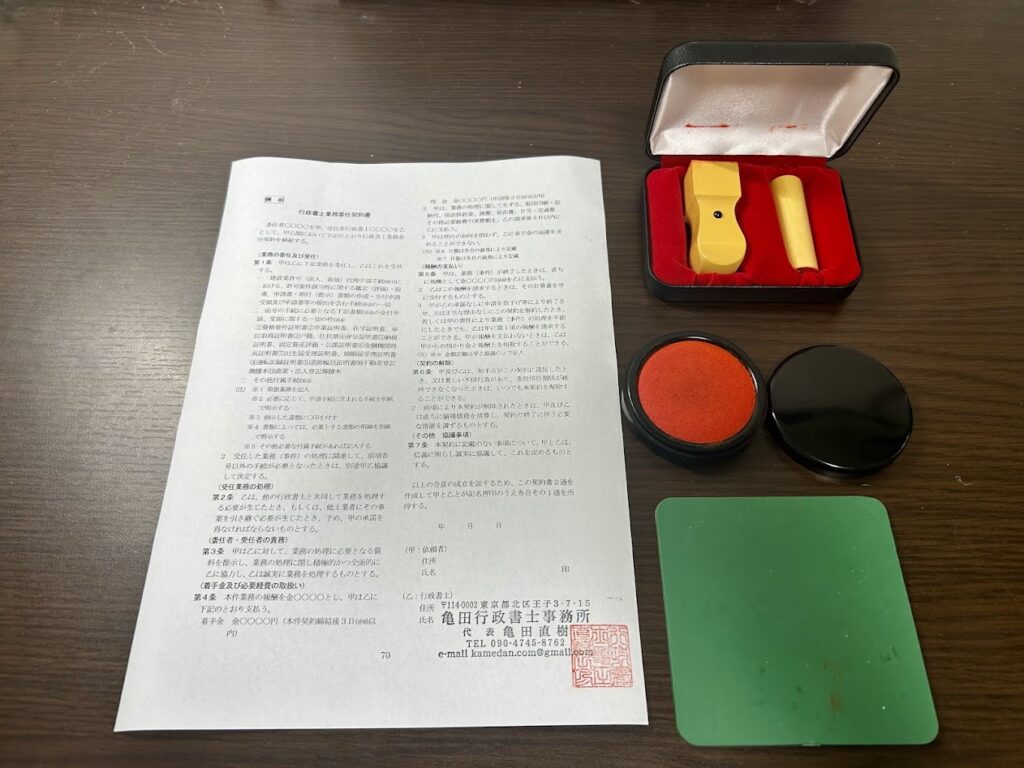
こんにちは、亀田行政書士事務所です。
今回は、当事務所で取り扱うことの多い 消費貸借契約 について、特に「一括弁済」と「分割弁済」の2種類の契約書を例に、ポイントを解説します。
1. 消費貸借契約とは?
消費貸借契約とは、貸主(債権者)が借主(債務者)に金銭や物を貸し渡し、借主がこれを受領した上で、同種・同等のものを返還することを約束する契約です。
一般的には金銭が対象となりますが、金銭に限定されるものではありません。借主は受け取った金銭を使用した後、同額または同種同等のものを返還する義務を負います。
従来、消費貸借契約は物の消費を前提とする契約とされていましたが、令和2年4月1日施行の改正民法により、当事者間の合意のみで成立することが認められています。
2. 一括弁済型の契約書
一括弁済型の消費貸借契約は、貸付金の返済を 一度に全額返す契約 です。
当事務所で作成する場合は、契約書第1条で貸付金の受渡しを確認し、第2条で返済方法(持参または指定口座への振込)を明確にします。振込手数料の負担者も明記します。
また、第3条には、借主が期限までに返済しない場合に 強制執行を承諾する条項 を入れることが一般的です。利息や遅延損害金が0%の場合でも、承諾条項や期限の利益喪失の明示は契約の安全性を高めます。
以下例文
消費貸借契約書(1回払い)
令和〇年〇月〇日
債権者:〇〇(以下「甲」という)
債務者:〇〇(以下「乙」という)
甲および乙は、以下の通り消費貸借契約(以下「本契約」という)を締結することを確認する。
第1条(貸付金)
甲は、乙に対して、金〇〇,〇〇〇円(〇〇〇円)を下記条件で貸し渡したことを確認する。
弁済期:令和〇年〇月〇日
利息:○%
遅延損害金:○%
第2条(弁済方法)
乙は、前条の貸付金を、弁済期に一括して以下の方法で甲に返済する。
甲に直接持参する
甲の指定する金融機関口座に振り込みにより支払う
振込手数料は乙の負担とする。
第3条(強制執行の承諾)
乙は、本契約に基づく債務の履行を確実にするため、弁済期に弁済を行わない場合には、直ちに強制執行を受けることを承諾する。
第4条(契約の効力)
本契約は、甲および乙が署名押印した日から効力を生じる。
署名押印
甲(債権者) 住所 署名・押印
乙(債務者) 住所 署名・押印
3. 分割弁済型の契約書
分割弁済型は、返済を 複数回に分けて行う契約 です。
契約書では、返済回数・毎月の返済額・返済期間を明確にします。また、利息や遅延損害金の条件を条項として盛り込み、期限の利益喪失や強制執行の承諾条項も設けます。
さらに当事務所では、次のような条項も追加しています:
- 繰上返済条項:借主が任意で残債務の一部または全額を早期に返済できることを明記
- 督促方法条項:返済が遅れた場合の催告手順や法的措置の流れを記載
これにより、貸主・借主双方にとって安心できる契約になります。
以下例文
消費貸借契約書(分割弁済・繰上返済・督促条項付き)
令和〇年〇月〇日
債権者:〇〇(以下「甲」という)
債務者:〇〇(以下「乙」という)
甲および乙は、以下の通り消費貸借契約(以下「本契約」という)を締結することを確認する。
第1条(貸付金)
甲は、乙に対して、金〇〇〇,〇〇〇円(〇〇〇円)を貸し渡し、乙はこれを受領して借り受けたことを確認する。
第2条(分割弁済)
乙は、前条の貸付金を、令和〇年〇月から令和〇年〇月まで、毎月末日限り、毎月金〇〇,〇〇〇円ずつ、合計〇回にわたり、甲の指定する金融機関口座に振り込みにより支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
前項の規定にかかわらず、乙は可能な限り早期に返済する努力をするものとする。
第3条(利息)
令和〇年〇月から令和〇年〇月までは無利息とする。
令和〇年〇月1日以降、弁済完了まで、年利5%の割合で利息を付すものとし、乙は毎月末日までに当月分の利息を甲の指定する金融機関口座に振り込みにより支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第4条(遅延損害金)
乙が期限内に弁済しなかった場合、または期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日の翌日から弁済完了まで、年〇%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第5条(期限の利益喪失)
乙が次の各号のいずれかに該当した場合、甲は通知や催告を要せず、乙は直ちに残債務全額を弁済するものとする。
分割払いの支払いを怠り、その金額が金〇〇〇,〇〇〇円に達した場合。ただし、事務上の都合(振込の遅延など)で入金が先送りになった場合を除く。
他の債務について仮差押え、仮処分、または強制執行を受けた場合。
他の債務について破産手続または民事再生手続開始決定を受けた場合。
国税滞納処分、またはこれに準ずる差押えを受けた場合。
第6条(督促方法)
乙が弁済を遅延した場合、甲はまず書面または電子メールにより、弁済の催告を行うことができる。
催告後、乙は遅延分および利息・遅延損害金を直ちに支払うものとする。
催告後も支払がない場合、甲は法的手段(内容証明送付、訴訟、強制執行など)を講じることができる。
第7条(繰上返済)
乙は、任意の時点で残債務の一部または全額を繰上げて返済することができる。
繰上返済を行う場合、事前に甲に通知し、振込により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
繰上返済により利息が未経過分ある場合、その利息は返済時点までの日割りで精算する。
第8条(強制執行の承諾)
乙は、本契約に基づく債務の履行を確実にするため、期限到来後に弁済を行わない場合、直ちに強制執行を受けることを承諾する。
第9条(契約の効力)
本契約は、甲および乙が署名押印した日から効力を生じる。
署名押印
甲(債権者) 住所 署名・押印
乙(債務者) 住所 署名・押印
4. 契約書作成のポイント
- 貸付金の受渡し確認
契約第1条で貸付金を確実に渡したことを記載することで、後日トラブルを防ぎます。 - 利息・遅延損害金・期限の利益喪失の明示
返済の遅延や不履行があった場合の対応を明確にしておくことが重要です。 - 強制執行承諾の条項
借主が返済しない場合に備え、強制執行を受けることを承諾する条項を入れることで、契約の実効性が高まります。 - 分割弁済では繰上返済・督促条項も検討
借主が早期返済する場合や、返済遅延時の手順を定めておくと安心です。
まとめ
消費貸借契約は、金銭の貸し借りを安全に行うための基本的な契約です。
一括弁済か分割弁済かによって条項の内容は変わりますが、いずれの場合も 貸付金の受渡し確認、利息・遅延損害金の明示、期限の利益喪失、強制執行承諾条項 が重要です。
当事務所では、個々の事情に応じて、トラブルになりにくい契約書の作成をサポートしています。
消費貸借契約の作成・公正証書化をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC