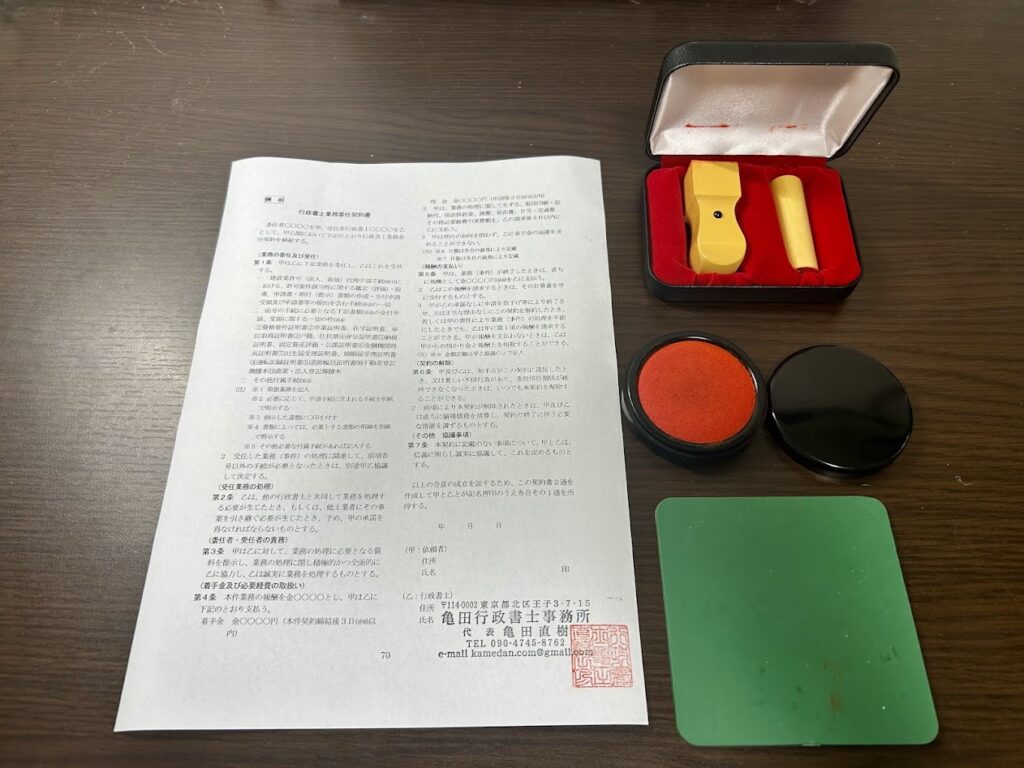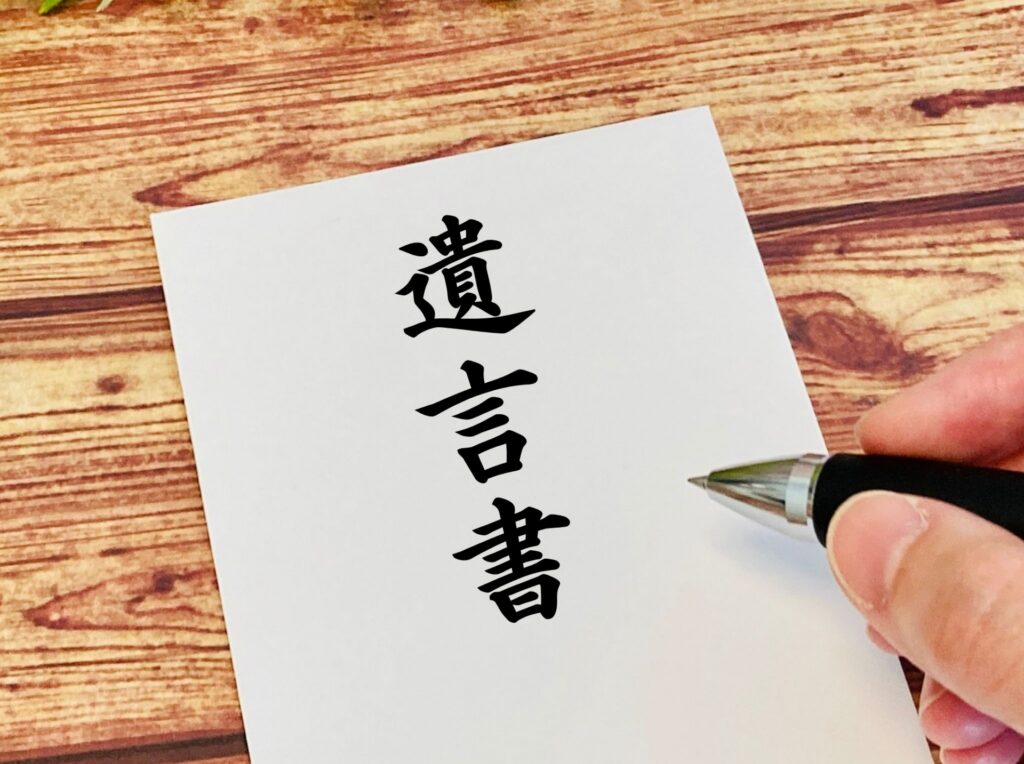
死後の委任事務契約において、委任者の意思と相続人の意思が異なり争いになるケースとして最も多いのは、葬儀や埋葬に関する事柄です。そのため、契約内容を明確に決め、文章として残しておくことが重要です。現状では、自分の葬儀について自ら決定し、葬儀社等と直接契約しておくことも可能です。可能であれば、そのようにしておくことをお勧めします。
死後の委任事務契約では、委任者の意思を尊重して受任者が行動できるよう、契約事項をしっかりと定めておくことが重要です。
死後の委任事務契約書 【例】
死後委任事務契約書
第1条(契約の趣旨)
委任者である甲は、乙に対し、令和0年0月0日以降の甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(委任事務の範囲)
乙は、甲の死亡後における次の事務を委任される。
- 親族や関係者への連絡事務
- 葬儀、埋葬及び永代供養に関する事務
- 医療費、入院費、老人ホーム等の施設利用料等、その他一切の債務弁済
- 入院費、保証金、入居一時金、その他一切の残債権の受領
- 同時に締結する委任契約及び任意後見契約における未処理事務、家財道具や生活用品の処分に関する事務
- 行政機関への届出等に関する事務
- 相続財産管理人の選任申し立て手続き
- 上記各事務に関する費用の支払い
2 乙は、本件死後事務委任を遂行するにあたり、必要に応じて代理人を選任できるものとする。
第3条(通夜・告別式)
通夜及び告別式は、乙が喪主として〇〇総合斎場にて家族葬で行うものとする。
第4条(納骨・埋葬・永代供養)
- 納骨・埋葬は〇〇所在地にて行う。
- 永代供養は〇〇寺にて行う。ただし、永代供養に関する事務は当該寺に依頼して終了するものとする。
第5条(費用の負担)
乙が本件死後事務を処理するために要する費用は、甲の負担とする。
第6条(報酬)
- 乙の本件死後事務処理に対する報酬は、金〇〇円(消費税別)を上限とし、本件死後事務契約終了時の甲の遺産から支払うものとする。
- 甲の預貯金の額が報酬額に満たない場合は、預貯金の範囲内で支払うものとする。
第7条(契約の変更)
甲は生存中、いつでも本件死後事務契約の変更を求めることができる。
第8条(契約の解除)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、本契約を解除できる。
- 乙が甲の財産を故意または過失により毀損し、その他乙の行為が甲に対して不法行為を構成し、信頼関係が破壊された場合
- 乙が本件死後事務を遂行することが困難となった場合
2 乙は、経済情勢の変化その他相当な理由により、契約の達成が不可能または著しく困難となった場合に限り、契約を解除できる。
第9条(委任者の死亡による効力)
- 甲が死亡した場合でも、本契約は終了せず、相続人は委任者の権利義務を承継する。
- 相続人は、前項の場合において、乙の自由権限行使により契約を解除することはできない。
第10条(契約の終了)
本契約は次の場合に終了する。
- 乙が死亡または破産手続開始決定を受けたとき
- 乙が後見開始または補佐開始の審判を受けたとき
- 甲及び乙が締結した委任契約及び任意後見契約が解除されたとき
- 本件死後事務のすべての任務が終了したとき
第11条(守秘義務)
乙は、本契約に関して知り得た秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
第12条(協議事項)
本契約及び任意後見契約に定めのない事項、疑義のある事項については、甲及び乙が協議して定める。
まとめ
死後事務委任契約は、普段あまり意識することのない「自分が亡くなった後のこと」をあらかじめ整理しておくための大切な契約です。
特に葬儀や埋葬、永代供養、財産整理などは、残された家族や親族の間で意見が分かれやすいものです。だからこそ、本人の意思を明確に文章で残し、信頼できる受任者に委任しておくことが、争いを防ぎ、円滑な手続きを実現する一番の方法です。
また、この契約を通じて、自分の意思を尊重してもらえる安心感は、本人だけでなく、残された家族にとっても大きな支えになります。日常生活では考えにくいことかもしれませんが、少し先の未来に備えて準備をしておくことは、思いやりのひとつと言えるでしょう。
「自分らしい最後」を実現するために、死後事務委任契約を活用してみてください。
- 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC