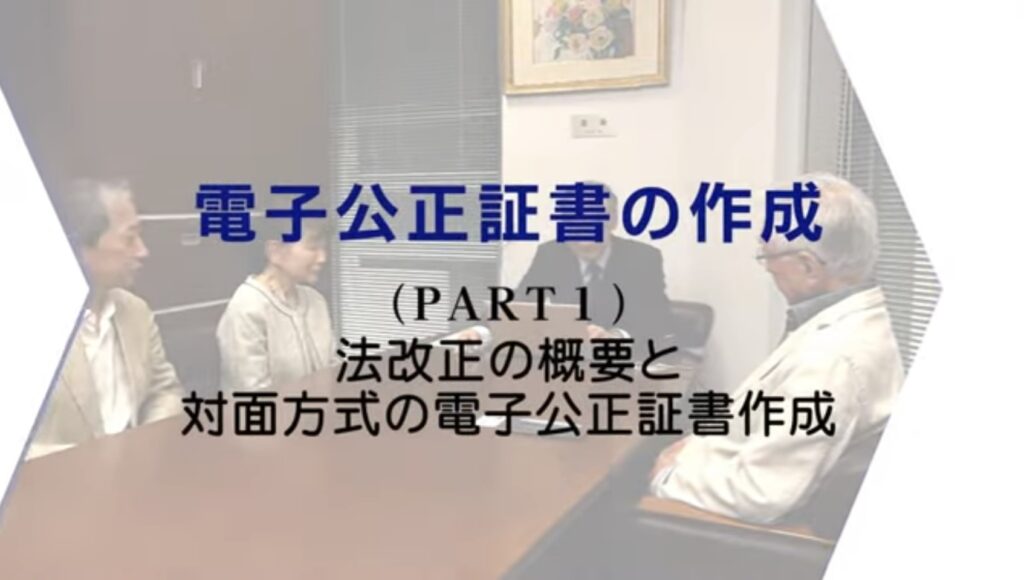認知症による資産の凍結と成年後見制度の役割
認知症が進行し、本人の判断能力が著しく低下した場合、各種契約行為が中断され、本人名義の財産について以下のような資産凍結状態が生じます。
- 不動産の売却や処分ができない
- 預貯金の管理・引き出しができない
- 自社株の売買や議決権行使ができない
- その他重要な契約行為ができない
このような状況で活用されるのが、「成年後見制度」です。成年後見制度は、本人の財産を保護しつつ、必要な管理を行う制度です。
成年後見制度の特徴と限界
① 本人の財産を「本人のために」維持・管理する制度である
成年後見人の主な役割は、本人の財産を守り、本人の生活や療養に必要な範囲内でこれを管理・使用することです。そのため、借入や投資などの積極的な財産活用は原則としてできません。
たとえば、本人が所有する不動産の建て替えや運用目的での借入、株式の売却などは「本人の生活の維持に直接関係しない」と見なされるため、家庭裁判所の許可が得られにくい、または後見人の判断で否認されることがあります。
特に、自社株の処分など専門的判断を伴うものについては、後見人(通常は弁護士や司法書士などの専門職)に委ねられることになり、家族の意向とは異なる結論が出されることも少なくありません。
② 家族への贈与・お年玉・お小遣いも原則不可
成年後見制度下(成年後見開始後)では、本人の財産は、本人の生活・療養・施設費用などに限定して使用されるべきとされています。
そのため、
- 家族への生前贈与
- 孫へのお年玉やお小遣い
- 遠方からお見舞いに来る家族の交通費・旅費の援助
といった出費は、「本人の利益にならない」と見なされ、家庭裁判所の許可が下りないことが大半です。
また、本人の生活環境をより良い施設に移す場合でも、「現在の施設で生活が成り立っている」という理由で、環境改善を目的とした施設変更のための費用支出が認められないケースもあります。
③ 制度が有効な場面
このような制約がある一方で、成年後見制度は以下のような場合に非常に有効です:
- 本人に身寄りがいない
- 家族が財産管理を行う体制が整っていない
- 財産管理のトラブルが生じている
つまり、家族がいない、または家族間での争いを防止するために第三者による客観的な管理が必要な場合に、成年後見制度は重要な役割を果たします。
遺言と成年後見制度を併用した実際の事例
【登場人物】
- 母(現在、認知症の状態。駅前の貸しビルを所有)
- 父(すでに他界)
- 長男(相談者。母との間の子)
- 母の前夫との子(現在は疎遠)
【背景】
相談者である長男は、母がかつて前夫との間に子どもがいることを懸念しており、母が元気なうちに「すべての財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成してもらっていました。
現在、母は認知症が進行し、高齢者施設に入居中です。駅前に所有する貸しビルが老朽化しており、テナントが減って収益が減少し、既存の借入金の返済にも支障が出ている状況です。
相談者は、貸しビルの立地の良さから、新たに借入をして建て替えを行い、収益性の高い物件として再生すれば、母の生活費にも充てられると考えていました。
また、母の生前からの意向であり、先祖代々の土地を守り続けたいという思いも強くありました。
【問題点】
しかしながら、以下の点が障害となりました。
- 遺言の効力は母の死亡後にしか発生しない
現在、母が認知症であっても存命である限り、遺言の内容は「効力を持たない」ため、相談者(長男)がビルの処分権を有しているわけではありません。 - 借入や建て替え等の行為は、後見人制度の枠外
このままでは対応が難しいため、やむなく成年後見制度の申し立てを行うことになりました。
申し立て時、家庭裁判所からは「本人と利害関係のない第三者が後見人に選任される可能性が高い」という説明がなされました。
【結果】
予想通り、長男ではなく弁護士が第三者後見人として選任されました。
相談者が後見人になることは叶いませんでした。
選任された弁護士に対して、長男はビルの建て替えや借入による再生計画を相談しましたが、後見人である弁護士は次のような提案をしました:
駅前ビルを売却し、その代金で借入金を返済し、残金でお母様を適切な認知症施設に入所させるのが最善である。
その結果、先祖代々の不動産は売却され、遺言で「全財産を長男に」と書かれていたにもかかわらず、長男の希望は叶いませんでした。
成年後見制度の限界と注意点
成年後見制度は、原則として遺言が存在する場合にはその内容を尊重するよう努めることとされていますが、後見人は「本人の現在の利益」を最優先に判断します。
遺言のとおりに対応してくれるとは限らず、個々の事情とその時点での最適判断により、遺言内容と反する結論に至ることもあります。
【結論】
成年後見制度は本人の財産保護において重要な制度ですが、
- 家族が希望する柔軟な資産管理や承継対策ができない
- 自由な贈与や投資が制限される
- 遺言内容の実現が阻まれることもある
といった課題があるため、制度の限界と目的をよく理解し、事前に適切な対策を講じることが重要です。
【※参考】任意後見制度と法定後見制度の違い ~認知症対策としての後見制度の選択~
高齢者の財産管理や生活支援をめぐる法的手段として「後見制度」がありますが、これは大きく分けて 「任意後見制度」 と 「法定後見制度」 の2種類があります。両者には目的や開始のタイミング、監督体制に明確な違いがあり、特に相続や財産保全の観点から制度選びが重要です。
以下の比較表でその違いを整理します。
| 項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 本人が判断能力を有しているうちに契約を結び、後に認知症などで判断能力が低下したときに裁判所へ申立てて開始 | すでに判断能力が低下している状態で、本人や家族が家庭裁判所へ申立てて開始 |
| 申立人 | 本人自身 | 家族、親族、自治体等 |
| 契約 | 公正証書で任意後見契約を締結 | 契約ではなく、裁判所による審判で選任 |
| 後見人の選任方法 | 本人が事前に指名できる | 裁判所が選任(家族以外の専門職が選ばれることも) |
| 財産管理の方針 | 本人の意思に基づく柔軟な支援。ただし、本人の財産を「守る」ことが前提であり、リスクを伴う積極運用は原則避けるべき。 | 財産の保全が最優先。リスクのある運用や契約行為は原則制限される。 |
| 監督体制 | 後見開始後に「任意後見監督人」が必ず選任され、後見人の行為をチェック | 裁判所の監督下。必要に応じて「後見監督人」が選任されることもある |
| 終了時期 | 本人が死亡したとき | 本人が死亡したとき |
任意後見の注意点:財産の積極運用はできるのか?
任意後見制度では、契約によって後見人の権限をある程度柔軟に定めることができますが、これはあくまで本人の「意思を尊重しつつ、その財産を守る」ことが前提です。
たとえば、本人が元気なうちに「将来的に投資用不動産の管理も任せたい」と希望していたとしても、判断能力が低下した後は、そのような積極的な財産運用(リスクを伴う投資など)は原則として認められにくくなります。任意後見監督人が就いていることで、後見人の判断にブレーキがかかるような仕組みが整備されており、本人の財産が不当に減少しないよう厳格に監視されます。
制度選択のポイント
- 「将来の不安に備えて、信頼できる人に自分の財産管理を任せたい」という方には、任意後見制度が有効です。
- 「すでに判断能力が不十分な親族がいて、急ぎ財産管理を開始したい」場合は、法定後見制度を選ぶ必要があります。
家族信託と成年後見制度の併用について
高齢者が認知症を発症し、判断能力が低下した場合、法的な意思決定を支援する制度として「成年後見制度」があります。しかし、その活用にあたっては、いくつかの注意点があります。
特に、※第三者後見人が選任されるケースでは以下のような違いが生じます。
① 成年後見制度のみを利用した場合
仮に成年後見制度だけを利用する場合、ご家族、例えば息子さんが親の財産を直接管理することはできません。成年後見人が財産管理権限を持つため、家族の意向と異なる形で財産が運用されることもあり得ます。特に上記のレインのように、第三者が後見人となった場合、柔軟な対応や家族の希望を反映させることが難しくなることがあります。
② 家族信託と成年後見制度を併用した場合
これに対し、家族信託と成年後見制度を併用することで、より柔軟な財産管理が可能になります。信託財産については、あらかじめ信託契約に基づいて、例えば息子さんを受託者として指定することで、親が認知症を発症しても、息子さんが信託財産の管理を継続できます。
成年後見人は受益者(認知症を発症した本人)としての権利に基づき関与するにとどまります。つまり、信託財産の管理そのものには成年後見人が直接関与することはありません。
ただし、信託財産以外の財産(預貯金、不動産など)については、成年後見制度の枠組みの中で成年後見人が管理することになり、家族が自由に動かすことはできません。
また、成年後見人は受益者としての法的権利を有するため、信託契約の内容についても慎重に設計する必要があります。特に、信託契約の中に成年後見人の権限や意思決定に配慮した条項を盛り込んでおくことが、後のトラブルを回避するために慎重な設計が必要となります。
まとめ:成年後見制度の限界と、信託との併用による対策の重要性
成年後見制度は、認知症等により判断能力が低下した方の財産を守るために重要な制度であり、身寄りのない高齢者や、家族間での財産トラブルを防止したい場合には有効に機能します。
しかし一方で、
- 柔軟な資産運用や承継対策が困難である
- 贈与や家族支援が原則として認められない
- 専門職後見人が選任されると、家族の意向が反映されにくくなる
- 遺言の内容が十分に尊重されないことがある
といった制限やリスクも抱えています。
そのため、高齢者が元気なうちに「誰に」「どの財産を」「どのように」託したいかを明確にし、家族信託などの制度と併用して対策を講じておくことが極めて重要です。
家族信託は、受託者を通じて財産の柔軟な管理・運用を実現でき、本人の意思を反映した財産承継を可能にします。成年後見制度と併用することで、信託財産については家族が継続して管理しつつ、それ以外の財産は成年後見制度によって法的保護を受けるという、補完的かつバランスの取れた対応が可能になります。
認知症対策や資産承継においては、それぞれの制度の特性と限界を正しく理解し、早めの準備と専門家の支援を受けた設計が、本人と家族の安心につながる道と言えるでしょう。
✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC