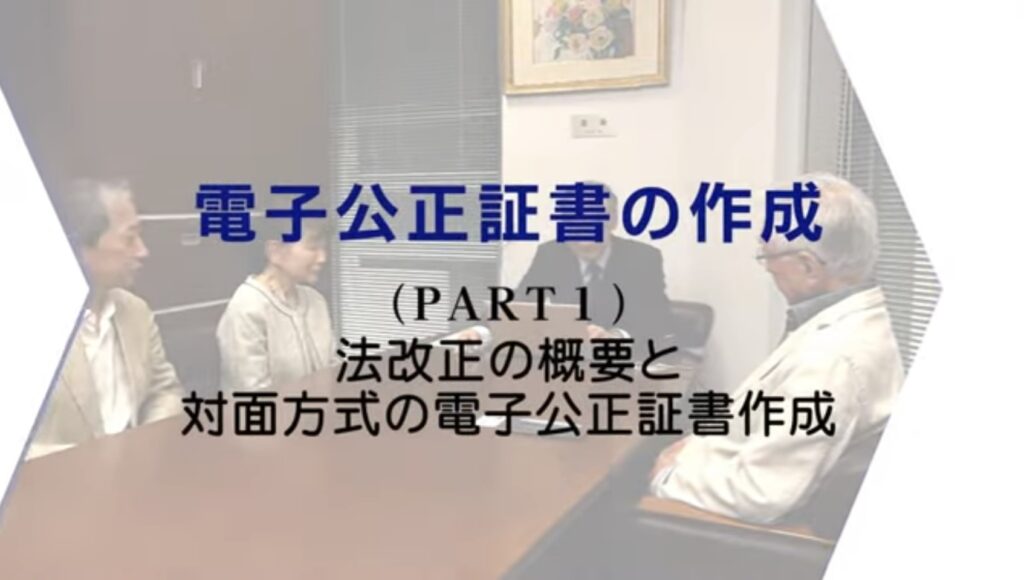こんにちは。亀田行政書士事務所の亀田です。
認知症などで本人の判断能力が低下すると、預貯金が凍結され、生活費や医療費の支払いが困難になることがあります。
そんなときに頼りになるのが成年後見制度ですが、すぐに利用できるわけではありません。今回は、制度の手続きや流れ、必要書類について解説します。
成年後見制度の申し立てから後見人選任までの流れ
- 申立書類の準備
- 申し立てには多くの書類が必要です。主な書類は以下の通りです:
- 申し立て事情説明書
- 家族関係図
- 親族の意見書
- 後見人候補者事情説明書
- 財産目録・相続財産目録・収支予定表
- 申立人・本人・候補者の戸籍謄本や住民票
- 本人の診断書・健康状態資料
- 本人の財産資料や相続財産に関する資料
- 申し立てには多くの書類が必要です。主な書類は以下の通りです:
- 家庭裁判所での面接・調査
- 申し立て日には、申立人・本人・後見候補者と調査官の面接が行われます
- 調査官による本人の心理調査や、親族への意向確認も行われます
- 必要に応じて医師等による鑑定が行われることもあります
- 後見開始の審判・後見人選任
- 調査結果を踏まえ、家庭裁判所が後見開始を決定
- 同時に後見人が選任されます
- 後見人候補者を推薦することはできますが、最終的に選ぶのは家庭裁判所です
- 家庭裁判所の判断に不服申し立てはできません
成年後見制度の特徴
- 制度は本人が亡くなるまで継続されます
- 後見人は、本人の財産を適切に管理する義務があります
- 後見人は年に1回、裁判所に対して後見事務の状況を報告する必要があります
まとめ
- 認知症などで判断能力が低下すると、預貯金の凍結や資産管理の問題が起きます
- 成年後見制度は、本人の財産を保護する制度であり、手続きには書類準備・家庭裁判所での調査・後見人選任が必要です
- 後見人は制度開始後、本人が亡くなるまで財産管理の責任を負います
ご相談ください
「親の預貯金が凍結されて困っている」
「成年後見制度を利用して、資産管理や生活費の支払いをスムーズにしたい」
そんなお悩みは、亀田行政書士事務所にご相談ください。
- 電話・メール・LINEで簡単予約可能
- 専門家が手続きの流れや必要書類を丁寧にご案内します
- ちょっと顔が大きめで、内気なところもある亀田が、丁寧にサポートします。
- ✅ 東京都北区 亀田行政書士事務所
- ✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- ✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
- 電話 090-4745-8762
- メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
- ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC
- 遺言書作成の流れ
- 遺言作成ヒアリングシートダウンロード