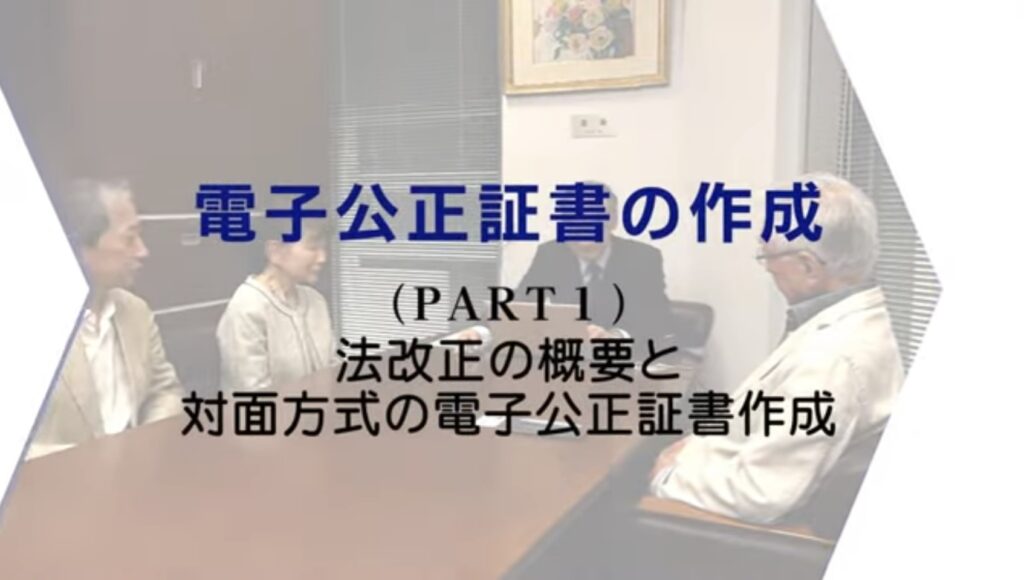家族信託(民事信託)の活用が広がる中で、「受益者連続型信託」と「遺留分侵害額請求」の関係は、相続設計において非常に重要なテーマです。特に、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を組む場合、第二次・第三次以降の受益者がどのように受益権を取得するか、そして遺留分請求がどの段階で可能になるかは、依頼者への説明でも欠かせません。
1. 受益者連続型信託の法律構成
後継ぎ遺贈型信託においては、第二次以降の受益者は先順位の受益者から受益権を引き継ぐのではなく、委託者から直接取得するという構成になります。
- 第2次受益者(例:妻)は、委託者の死亡時に、存続期間が不確定(自身の死亡まで)の受益権を取得
- 第3次受益者(例:長男)も、委託者の死亡時に、存続期間が不確定(妻の死亡から自身の死亡まで)の受益権を取得
遺留分算定の基準時は、いずれの受益者も委託者(第1次受益者)の死亡時であり、第2次受益者の死亡時ではありません。
2. 遺留分侵害額請求との関係
立法担当者の解釈によれば、第二相続時には遺留分侵害額請求はできないとされています。
しかし、最高裁判例は存在せず、実務上は一次相続・二次相続ともに遺留分侵害額請求の可能性を考慮すべきとされています。
3. 判例の動向と実務上の注意点
参考となる事例として、平成30年9月12日 東京地裁判決があります。
【要旨】
- 信託契約のうち、経済的利益の分配が想定されない自宅不動産・山林等を目的財産に含めた部分は、公序良俗に反し無効(遺留分制度潜脱の意図あり)
- 一方で、収益不動産や信託金銭を含めた部分は有効
- 遺留分減殺の対象は「信託財産」ではなく、実質的に移転される受益権
※この事案は相続法改正前の遺留分減殺請求に関するもので、2019年改正後は金銭債権化された「遺留分侵害額請求」となっています。
なお、この東京地裁判決は控訴後に東京高裁で和解が成立し、一審判決の効力は消滅しています。
4. 現状とプロの対応方針
2024年8月時点において、信託と遺留分侵害額請求の関係についての最高裁判例は存在しません。
そのため、プロとしては
- 遺留分侵害額請求ができない解釈も可能であること
- しかし判例によって覆る可能性があること
を依頼者に説明し、その前提で信託契約書を作成する必要があります。
まとめ
- 受益者連続型信託は、相続対策として有効な一方、遺留分請求との関係で法的リスクが残る
- 現状では最高裁判例がなく、実務上は一次・二次相続いずれも遺留分侵害額請求の可能性を考慮すべき
- 契約書作成時には、依頼者にリスクを十分に説明することが重要
亀田行政書士事務所では、最新の判例や法改正動向を踏まえ、依頼者の状況に最適な信託契約書をご提案します。相続や家族信託に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC